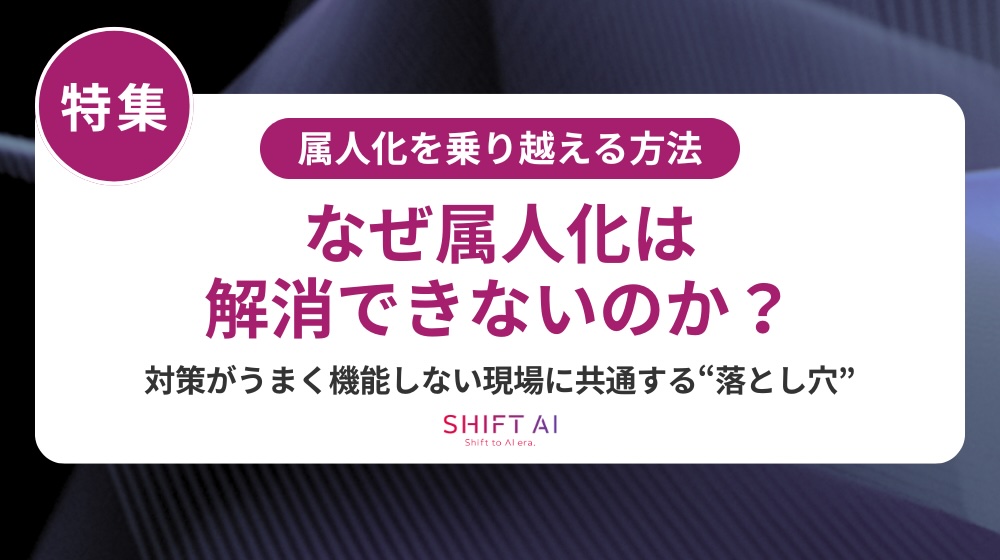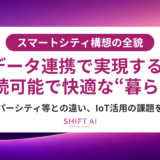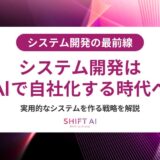「この作業、自分しかやり方を知らない」
――そんな状態、放置していませんか?
業務が回っているように見えても、担当者が突然休んだり退職した途端に業務がストップする。
それは、属人化が進んでいる組織に起こる典型的なトラブルです。
「引き継ぎができない」「教える時間がない」「書くのが面倒」
そんな理由でマニュアル作成が後回しになっている現場も多いのではないでしょうか。
ですが、実はマニュアル化は“仕組み”として属人化を解消する一番手軽な方法です。
しかも、最初の一歩さえ踏み出せれば、特別なスキルがなくても誰でも始められます。
本記事では、属人化のリスクやマニュアル化のメリットはもちろん、今日から取り組めるマニュアル作成のステップやテンプレート、さらに生成AIを活用した時短のコツまで、実践的にわかりやすく解説します。
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
なぜ今、属人化された業務のマニュアル化が急務なのか
「なんとなく業務が回っている」
それだけで安心してはいけません。
属人化された業務は、一人の担当者に業務知識や手順が集中している状態。
いざその担当者が休んだり、退職したりすれば、他の誰も対応できずに業務が止まる──そんな危機がすぐそこに潜んでいます。
ではなぜ、マニュアル化が属人化の解消に有効なのでしょうか?
ここでは、属人化のリスクと、マニュアル化によって得られる具体的な効果を整理します。
属人化がもたらすリスクとは
属人化によって起きるリスクは、単に「引き継ぎができない」にとどまりません。
- 業務停止リスク:担当者の不在で業務が進まなくなる
- 品質のばらつき:誰が対応するかで成果や判断が変わる
- 教育コストの増加:新任者に一から説明し直す非効率
- 社員のストレス増加:頼られすぎる側の精神的負担
このように、属人化は個人と組織の両方に悪影響を与える状態です。
特に近年では、テレワークや人材の流動性が高まり、「誰がいつまで担当してくれるかわからない」ことも多くなっています。
マニュアル化で得られる3つの効果
マニュアル化とは、業務手順や判断基準を見える化・形式化することです。
これにより、次のような効果が得られます。
- 誰でも業務を再現できる
→担当者に依存しない体制が整う - 引き継ぎや教育がスムーズになる
→人材交代のたびに説明する手間が減る - ミスや属人リスクが激減する
→手順の標準化により作業品質が安定
これらの効果は、単なる“属人化の解消”にとどまらず、組織全体の生産性や心理的安全性の向上にも直結します。
関連記事:属人化を防ぐ効果的な方法|AI活用で業務標準化を実現する実践ガイド
「とりあえずこれだけ」でOK!マニュアル化の基本ステップ
「マニュアル化が必要なのはわかっているけど、時間も人手も足りない」
そんな声をよく聞きます。
そこで本章では、今すぐ始められて、最低限の効果が得られるマニュアル化の3ステップをご紹介します。
複雑なシステムや高度な設計は不要。まずは“形にすること”が最優先です。
Step1:対象業務を洗い出す(属人化チェックリスト付き)
最初に取り組むべきは、どの業務からマニュアル化すべきかを見極めることです。
以下のような業務は、属人化の温床になりやすいため優先度が高いです。
属人化の兆候がある業務チェックリスト
- 特定の人しかやり方を知らない業務
- 手順が複雑で、口頭でしか伝わっていない作業
- 担当者が不在になると業務が止まる内容
- 頻度は低いが、対応ミスが致命的になる処理
- 「前任者しかわからない」と言われている業務
まずはこのような業務を3〜5件ピックアップすることから始めましょう。
最初からすべてを網羅しようとすると挫折します。
小さく始めて、徐々に広げていくのが成功の秘訣です。
Step2:「作業の流れ」と「判断基準」に分けて整理する
マニュアルをつくる際、多くの方が「手順だけ書けばいい」と思いがちです。
しかし、実際の属人化の原因は「どう判断しているのか」が共有されていないことにあります。
たとえば、
- 「取引先によって対応を変える」
- 「場合によっては承認を飛ばす」
- 「AとBのどちらかを選ぶが、判断は個人に任せていた」
こうした“判断のルール”を明文化することが、属人化の本質的解消につながります。
Step3:テンプレートを使って“形式化”する
情報を洗い出したら、誰でも読みやすく、更新しやすい形式にまとめましょう。
おすすめは以下のような簡易テンプレートです。
業務マニュアル基本テンプレート例
- 業務名:〇〇業務(例:請求書の発行処理)
- 目的:何のために行っているか
- 作業手順(時系列):箇条書きまたは番号順で明記
- 判断ポイント:条件付きの分岐や例外ルール
- 使用ツール・システム:使用画面・URLなども明記
- 更新履歴:最終更新日・更新者名
この形式に沿ってまとめていくだけで、誰が見ても「迷わず進める」業務マニュアルが完成します。
実際に作ってみる|15分でできる業務マニュアルの書き方
ここまででマニュアル化のステップは理解できたけれど、
「実際どう書けばいいの?」という方のために、実例ベースでの作成イメージを紹介します。
マニュアルは完璧を目指さず、まず“ざっくり”形にすることが重要です。
「時間がない」「整ったテンプレがない」場合でも、15分あれば十分スタート可能です。
事例1|バックオフィス業務(経費精算の手順)
業務名:経費精算の登録作業
- 目的:社員が立替経費を申請・処理できるようにする
- 手順:
①社内ポータルにログイン
②経費申請フォームを開く
③日付・金額・用途を入力し、領収書を添付
④上長を選択し「申請」ボタンを押す - 判断基準:
・1,000円未満の備品は申請不要
・領収書がない場合は別途備考に理由を記載 - 使用ツール:経費精算システム(リンク記載)
事例2|営業現場(問い合わせ対応のフロー)
業務名:初回問い合わせ対応(電話)
- 目的:営業部宛ての電話問合せへの基本対応
- 手順:
①名乗り+会社名・担当者名を確認
②用件のヒアリング(要点をメモ)
③担当者がいれば内線へ転送、いなければ「後ほど折り返し」と伝える
④問合せ内容をCRMに記録し、担当者に通知 - 判断基準:
・資料請求希望はマーケ部へ転送
・採用関連は人事直通に回す - 使用ツール:電話・社内CRM
事例3|システム操作(生成AIツールの操作マニュアル)
業務名:AIチャットボットによる社内Q&A更新
- 目的:毎週のよくある質問をAIに登録し、回答精度を高める
- 手順:
①前週のSlackログから頻出質問を抽出
②回答が曖昧なものを一覧化
③管理画面で質問と想定回答を登録し「学習」ボタンを押す - 判断基準:
・同義語が多い質問は1つに集約
・業務ルール変更に関わる内容は事前に部門長に確認 - 使用ツール:AIチャット運用システム(例:NotionAI、Karakuri等)
このように、シンプルな構成+判断の基準を言語化するだけでも、立派なマニュアルになります。
テンプレートや整ったフォーマットがなくても、まずは「誰が見ても業務を再現できる」ことを目指すことが重要です。
ありがちな失敗パターンと、マニュアル化を続けるコツ
マニュアル化は、作っただけでは意味がありません。
むしろ「せっかく作ったのに誰も使わない」「気づけば内容が古くなっていた」という声も多く、運用フェーズでつまずくケースが非常に多いのが実情です。
ここでは、属人化解消の効果をきちんと発揮させるために、マニュアル化でよくある失敗と、その対策法を整理します。
「とりあえず書いただけ」で終わる
マニュアルが形骸化する最も大きな原因は、“完成して終わり”と思ってしまうことです。
業務は日々変化します。ツールが変わったり、運用ルールが微修正されたり…。
放っておけば、マニュアルはすぐに「役に立たない古い情報」になってしまいます。
対策:「更新前提」で作ること
- 最終更新日・担当者名を明記する
- 一部だけでも簡単に修正できる形式(例:クラウド共有・Wiki型)にする
現場が使わない・見ない
「現場の誰も読まない」
「あるけど探しづらい」
マニュアルが埋もれてしまう要因は、形式より“使われ方”にあります。
対策:現場で“使える設計”にすること
- 手順だけでなく“判断基準”をセットにする(例:ケース分岐)
- 「見やすい場所」に置く(ツール内リンク、社内ポータルなど)
- 必要な情報だけを素早く探せる構成にする(目次・検索性)
半年に一度のレビュー設計を入れておく
マニュアルを“仕組み”として生かすには、更新の習慣化=運用ルールの設計が欠かせません。
対策:定期レビューサイクルを組み込む
- 半年に1度、各部署でマニュアルレビュー会を開催
- 「現状と合っているか」「もっと簡素化できないか」などをチェック
- その場で修正まで行う小さな改善ループを回す
マニュアルは“完成品”ではなく、現場とともに育てる「動く資産」です。
属人化を本質的に解消するには、継続的な見直しを通じて、「使われる・更新される文化」を組織内に定着させることが重要です。
生成AIを使えば、マニュアル化はもっと簡単にできる
「マニュアルをつくる時間がない」
「書き方がわからない」
そんな悩みも、生成AIを活用すれば大きく軽減できます。
実は今、マニュアル作成や業務の見える化にAIを使う企業が急増しています。
なぜなら、AIは“面倒”“難しい”“時間がかかる”といった壁を乗り越える最強のアシスタントになるからです。
ここでは、属人化解消の強力な味方となる、生成AIの活用アイデアを3つご紹介します。
会話形式で手順書をつくる(Chat GPT活用)
ChatGPTのような生成AIに、業務の流れを説明するだけで、
読みやすいマニュアルの素案を自動生成することができます。
例
「経費精算の申請手順をマニュアル形式にまとめて」
→目的・手順・判断ポイントを含めた文章を自動生成
活用のコツ
- 現場担当が「話すだけ」で作れる
- 説明内容は短くてもOK。AIが補完して構造化してくれる
議事録や業務記録から自動生成する
会議の音声記録や、チャットの業務報告をもとに、
業務プロセスやナレッジをマニュアルに変換することも可能です。
例
- Zoomの録音データ→AI文字起こし→要点抽出→手順書生成
- SlackのQ&A履歴→AIがよくある質問・回答集としてまとめる
効果
- 何度も同じ説明をする負担を削減
- 暗黙知を形式知化してナレッジ共有できる
ナレッジをAIチャットボット化する
さらに一歩進めて、マニュアルそのものをAIチャットボットとして運用することも可能です。
社員が業務中に「○○の手順は?」「例外処理はどうする?」と質問すれば、AIが即座に該当マニュアルや手順を返答します。
例
- NotionAI、Karakuri、HelpfeelなどのAI活用型FAQツール
- 社内専用のChatGPTAPI活用による回答bot
効果
- “探す手間”をなくし、必要な情報に瞬時にアクセス可能
- 業務属人化の「聞いたら終わり」構造を“誰でも検索できる”仕組みに変える
マニュアルを「書く」から「話す」へ。
ナレッジを「記録」から「使える仕組み」へ。
属人化を解消し、誰もが働きやすい職場環境をつくるために、生成AIの力を活かすべき時代が来ています。
関連記事:生成AIを現場で“使える仕組み”にする方法|導入ステップはこう描く!【チェックリスト付き】
まとめ|マニュアル化は“後回し”にしない方が得
「忙しいから」「時間がないから」
そうして後回しにされがちなマニュアル化ですが、属人化を放置したままでは、いずれ“もっと大きな損失”が訪れます。
業務が止まる、引き継ぎができない、ミスが増える――
すべて、マニュアルが“なかったから”起きる問題です。
逆に言えば、たった15分の作業でも「誰かが再現できる状態」にしておくことで、組織のリスクを大きく減らすことができます。
そして今は、テンプレートや生成AIの活用によって、マニュアル化のハードルは驚くほど低くなっています。まずは小さな業務から。
1つの業務を見える化するだけでも、現場の属人化は確実に減らせます。
- Qマニュアルがなくても業務が回っているのに、本当に必要ですか?
- A
一見業務が回っているように見えても、担当者が不在になると突然止まるリスクがあるのが属人化の怖さです。
マニュアルがあれば、誰でも業務を再現できる仕組みをつくることができ、休職・退職・異動などの際にもスムーズに引き継ぎが可能になります。
- Qマニュアルをつくる時間がありません。最低限どこから始めればいいですか?
- A
まずは「誰かに引き継げない業務」だけを3つほどピックアップして、
「作業手順+判断ポイント」の2点を箇条書きで整理するだけでも十分です。
完璧なフォーマットでなくても、「他の人が読んで再現できる」ことが目的です。
- Qマニュアルが更新されず古くなってしまいます。どうすれば継続できますか?
- A
おすすめは、半年に1回の定期レビュータイミングをあらかじめ設定しておくことです。
各部署でマニュアル確認のルーチンをつくることで、“作って終わり”にならず、「常に使える状態」を保つ運用が可能になります。
- Qマニュアル作成に生成AIはどう活用できますか?
- A
Chat GPTなどの生成AIを使えば、「話すだけで手順書を自動作成」したり、
過去のチャットや議事録からよくある質問と回答をまとめたりできます。
さらに、ナレッジをAIチャットボットとして運用することも可能です。
属人化を防ぐ手段として、今後の業務マニュアル作成における必須ツールになるでしょう。