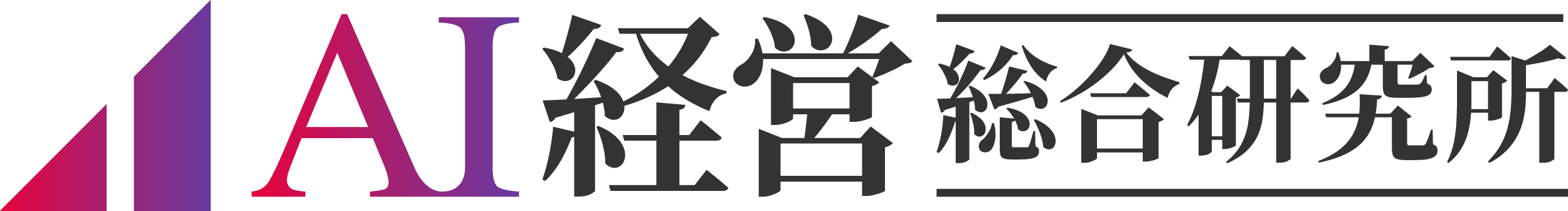日々増え続ける「問い合わせ対応」や「社内のFAQ対応」。対応品質を維持しながら、限られた人員でこれらの業務をこなすのは、今や多くの企業にとって大きな課題です。
こうした背景から、近年注目を集めているのが 「生成AIを活用したサポートチャットボット」です。
従来のルール型チャットボットとは異なり、生成AIチャットボットは曖昧な質問にも柔軟に対応し、ナレッジベースとの連携によって問い合わせ対応の“自動化・省力化・品質向上”を同時に実現します。
しかし一方で、
- どのようなツールを選べばよいのか?
- 自社業務にどう適用すればよいのか?
- 社内展開にはどんな準備が必要なのか?
といった疑問や不安も少なくありません。
この記事では、そんな方向けに、
- 生成AIサポートチャットボットの基本と特徴
- 具体的な活用シーン
- 導入時に検討すべきポイント
- 最新ツール10選と選び方の比較
- 社内展開を成功させる運用設計のコツ
を実務に役立つ視点から解説します。
生成AIを使ったチャット対応の「第一歩」を踏み出すための、実践的なガイドとしてご活用ください。
生成AIツール全般の業務活用を広く知りたい方は、こちらの記事も参考になります:
👉 企業向け生成AIツール15選【2025最新】選び方から導入まで解説
生成AIサポートチャットボットとは?従来型との違いと注目される背景
まずは生成AIのサポートチャットボットについて解説します。
いま注目を集める「生成AI × チャットボット」の新しい形
生成AIサポートチャットボットとは、ChatGPTなどに代表される生成AIの技術を活用して、問い合わせ対応や社内FAQへの回答を自然な言葉で自動生成するチャットボットです。
単なる定型文の返答ではなく、質問の文脈や意図を読み取り、柔軟に回答できるのが大きな特長です。
こうした性能を背景に、従来型のチャットボットでは対応しきれなかった領域にも対応できるツールとして、企業のカスタマーサポートや社内ヘルプデスクで導入が加速しています。
生成AIチャットボットと従来型チャットボットの違いとは?
ここでは、よく混同されがちな「従来型チャットボット」と「生成AIサポートチャットボット」の違いを整理します。導入検討を進める上で、それぞれの仕組みと特長を理解しておくことが重要です。
| 比較項目 | 従来型チャットボット | 生成AIサポートチャットボット |
| 回答方法 | ルールベース/定型文 | 自然言語による動的生成 |
| 対応範囲 | FAQなどの定型質問 | あいまい・複雑な質問にも対応 |
| シナリオ設計 | 必須(設計に手間) | 最小限(ナレッジ連携で対応) |
| 導入後の更新 | 都度ルール修正が必要 | ナレッジの更新だけで済むことも |
| 初期コスト | 比較的低い | 内容により高くなるが柔軟性◎ |
このように、生成AIを活用したチャットボットは学習と応用”ができる存在ともいえ、定型業務の自動化だけでなく、非定型な問い合わせや自然な対話の対応力という観点でも従来型を大きく上回っています。
なぜいま、生成AIサポートチャットボットが導入され始めているのか?
生成AI型のチャットボットは、単なるテクノロジートレンドではなく、ビジネス上の課題を解決する手段として、以下のような背景から注目されています。
- 24時間対応・人手不足の両立ニーズ
「いつでも誰でも」対応できる仕組みが求められるなか、AIが最前線の窓口として機能 - サポート品質とコストの両立
教育不要で対応品質を保ち、属人化リスクも回避可能 - 技術の進化による実用レベルへの到達
ChatGPTの登場以降、生成AIはビジネス利用に耐えうる精度と安定性を獲得
このように、今まさに「問い合わせ対応の在り方そのもの」が見直されており、生成AIチャットボットの導入が、業務変革の第一歩として位置づけられつつあるのです。
生成AIサポートチャットボットが活躍する主な業務領域
生成AIサポートチャットボットの導入が進む背景には、その汎用性の高さと応用範囲の広さがあります。これまで人の手で対応していた問い合わせ業務の多くが、生成AIの力によって自動化・効率化できるようになりつつあります。
ここでは、企業で特に活用が進んでいる代表的な3つの領域をご紹介します。
顧客からの問い合わせ対応(カスタマーサポート)
カスタマーサポート部門では、商品の仕様確認、手続き方法、トラブル対応など、繰り返し発生する定型的な質問が一定数存在します。
生成AIチャットボットを活用することで、
- 24時間365日の初動対応を自動化
- 人手では対応しきれない“ピーク時の問い合わせ”にも柔軟に対応
- 顧客満足度の向上と同時に、対応コストの削減が可能
といった効果が期待できます。
社内ヘルプデスク(情シス・人事・経理など)
社内からの「パスワードを忘れた」「勤怠の申請方法を教えて」など、ナレッジに基づく定型質問への対応も、生成AIチャットボットが得意とする領域です。
情シス・人事・経理部門などが対応していた業務を代替することで、
- 担当者の工数削減
- 情報の属人化防止
- 社員からの問い合わせに即時対応
といった業務効率化と対応品質の標準化が実現できます。
社内ナレッジ検索・マニュアル提供の自動化
業務マニュアルや社内規定などの情報にアクセスしづらい環境では、「どこに何が書いてあるのかわからない」といった声が現場から上がりがちです。
生成AIチャットボットと社内ナレッジベースを連携させることで、
- 複数文書の中から、該当箇所を自然文で要約・回答
- 社員が“調べずに聞ける”状態を構築
- 最新のマニュアル情報を一元化・再利用
といった、ナレッジ活用の最大化が可能になります。
このように、生成AIサポートチャットボットは、「顧客対応の最前線」から「社内業務の裏方」まで幅広い場面で活用できるツールです。
生成AIサポートチャットボットおすすめ9選【比較表+詳細解説付き】
生成AIサポートチャットボットは用途によって選ぶべきものが変わります。以下では10の代表ツールを比較表で整理したうえ、ツールごとに特長・導入ポイント・有効シナリオを詳しく解説します。
| ツール名 | 特徴 | 対応範囲 | 価格帯 | 日本語対応 | 得意領域 |
| ChatGPT API | 柔軟な応答生成、拡張性◎ | 汎用 | 従量制 | ◎ | PoC/開発者向け |
| hitTO AI | 社内FAQに特化、導入が簡単 | 社内 | 月額(中) | ◎ | 情シス・人事 |
| PKSHA Chatbot | セキュリティ高、自治体・金融導入多数 | 社外 | 中〜高 | ◎ | 公共・金融 |
| Bedore | 高精度対話で顧客満足度向上 | 社外 | 中〜高 | ◎ | EC・小売 |
| KIBIT | ロジック処理・文章解釈力に強み | 社内 | 中 | ◎ | ナレッジ検索 |
| Mona(SHIFT AI) | カスタム支援/PoC設計に対応 | 社内外 | 要相談 | ◎ | 全社展開 |
| ChatDealer | シンプル操作、導入ハードルが低い | 社外 | 低〜中 | ◎ | 中小企業 |
| Allganize | 高精度の検索型AI、多文書対応 | 社内外 | 中〜高 | ◎ | 多拠点・大企業 |
| Tactiq | 多言語AI対応、グローバル拠点向け | 海外拠点 | 低 | ◯ | BPO・外資系 |
ChatGPT API(OpenAI)
ChatGPT APIは、OpenAIの強力な生成AIを自社のチャットボットに組み込めるサービスです。高度な対話設計や外部システム連携が可能で、PoCや独自機能の開発を意図する企業に最適です。自由度が高い一方、技術リソースや運用監視体制の整備が求められる点は注意が必要です。詳細はChatGPT APIをご覧ください。
hitTO AI(株式会社ジェナ)
hitTO AIは社内FAQやヘルプデスク業務に特化して設計されたチャットボットです。Microsoft TeamsやSlackとの標準連携により導入がスムーズで、IT部門に頼らず現場スタートが可能です。シンプルな管理画面で運用も運用も負担が少なく、定型問対応を効率化したい企業に好適です。詳細はhitTO AIをご確認ください。
PKSHA Chatbot(株式会社PKSHA Technology)
高いセキュリティ基準を満たすPKSHA Chatbotは、金融機関や自治体でも多数採用されています。LINEなどの外部チャネル対応も可能で、公共・顧客向け窓口での利用に向いています。堅牢なシステムと柔軟なカスタマイズ性を兼ね備えており、安心して長期運用ができます。詳細はPKSHA Chatbotをご覧ください。
Bedore(ベドア)
Bedoreは、特にECや小売業界での導入実績が豊富なツールです。自然な日本語の対話生成と強力な会話履歴分析機能により、顧客満足度を高めます。日常の問い合わせからキャンペーン案内まで、人に近い応答で接客力を向上させます。詳細はBedoreをご参照ください。
MANA(NTTドコモ)
MANAはGPT‑4をベースとした高度な会話エンジンを搭載しています。複雑な業務や多要素を理解する役割に強く、大規模組織や社外顧客対応にも適しています。対話精度が高く、自然な回答が求められる場面で成果が期待できる一方、コスト面はやや高めです。詳細はMANAをご確認ください。
KIBIT(FRONTEO)
KIBITは専門的な文章解析力に長け、法務やマニュアル活用の現場で力を発揮します。社内文書を対象に、曖昧な表現からも正確な答えを引き出せます。懸念事項やコンプライアンス上の質問在でも、信頼性の高い応答が得られる点が強みです。詳細はKIBITをご参照ください。
ChatDealer(エーアイスクエア)
ChatDealerは初心者でも使いやすく、導入の敷居が低いチャットボットです。FAQ自動化や問い合わせ一次対応の導入にスピード感があり、中小企業に特に受け入れられやすい構成です。管理が容易で、トライアル的な運用を始める際には最適な選択肢の一つです。詳細はChatDealerをご参照ください。
Allganize(オルガナイズ)
Allganizeは大量ドキュメントを扱う大企業や多拠点企業に向いています。大量の文章から必要な情報を抽出し、複数言語での運用も可能です。高度なナレッジ検索機能により、社内情報の利活用を一気に加速できます。詳細はAllganizeをご覧ください。
Tactiq
Tactiqは多言語対応に強く、国際的な問い合わせ対応に最適です。英語だけでなく日本語への自然翻訳も実現し、海外拠点やグローバル企業にフィットします。多文化・多言語環境でもストレスのない対話を提供できます。詳細はTactiqをご確認ください。
📘 ツール選定に迷ったら?
「どれが自社に合うか分からない…」
「技術選定だけでなく運用体制も整えたい…」
という企業の方には、ツール選定から社内展開・教育までを総合的に支援する研修プログラムがおすすめです。
\ 組織に定着する生成AI導入の進め方を資料で見る /
生成AIサポートチャットボット導入のメリットと留意点
生成AIサポートチャットボットの導入は、単なる業務の自動化にとどまりません。「対応のスピード」「内容の精度」「ナレッジの再利用」といった複数の価値を同時に実現できる点が、他の自動化手段とは異なる強みです。
一方で、誤回答リスクやナレッジ整備といった運用面の課題も存在するため、導入にあたってはメリットと留意点の両面を理解しておくことが重要です。
導入メリット①:問い合わせ対応の工数削減
問い合わせの初期対応や定型的な質問に自動で応えることで、担当者の対応工数を大幅に削減できます。特に一次対応が集中する時間帯や繁忙期など、人手不足をカバーしつつ対応遅延を防げるのが大きな利点です。
導入メリット②:対応品質の標準化と属人化の解消
生成AIチャットボットは、登録されたナレッジに基づいて誰に対しても均一な品質で回答することができます。属人的な対応のばらつきや引き継ぎミスのリスクが減り、対応精度を安定的に保つ体制が構築できます。
導入メリット③:ナレッジの活用と蓄積を促進
FAQやマニュアルなどのドキュメントをチャットボットに連携することで、「検索せずにすぐ聞ける」仕組みを実現できます。さらに、やり取りの履歴から新たな質問パターンを見つけ出し、ナレッジの更新・改善にもつなげられるのが、生成AIならではの利点です。
留意点①:誤回答リスクと監視体制の整備
生成AIは文脈理解に長けている一方で、事実と異なる回答(いわゆる“ハルシネーション”)を生成する可能性があります。業務での活用には、正確なナレッジとの連携に加え、運用管理や定期的なモニタリング体制の構築が不可欠です。
留意点②:ナレッジベースの整備とメンテナンス
AIの精度を左右するのが、元となるナレッジの質と構成です。情報が古かったり、粒度が不揃いだったりすると、不適切な回答や曖昧な応答につながるリスクがあります。導入時には、社内ドキュメントやFAQの棚卸しと整理が重要です。
留意点③:社内リテラシーと活用体制の育成
AIツールは入れただけでは成果が出ません。利用する社員が「どう質問すれば適切な答えが返るか」を理解し、チームで運用できる体制があってこそ、ツールの価値が引き出されます。そのためには、教育・研修によるAIリテラシーの底上げもセットで検討する必要があります。
📘 導入と運用を同時に考えるなら研修が有効です
社内にノウハウがなくても大丈夫。導入前の検討段階から、ナレッジ整備・運用設計・研修支援までを一気通貫でサポートします。
\ 組織に定着する生成AI導入の進め方を資料で見る /
生成AIサポートチャットボットの導入ステップ【スモールスタート推奨】
生成AIサポートチャットボットは、便利な一方で設計や運用を誤ると「使われないツール」になってしまいます。
そのため、最初から完璧を目指すのではなく、スモールスタートで効果を確認しながら改善していく進め方が重要です。
ここでは、導入時に押さえるべき4つの基本ステップを紹介します。
ステップ1:目的と活用領域の明確化
まずは、「どの業務に、どんな目的でチャットボットを導入するのか」を明確にしましょう。
問い合わせ対応なのか、社内FAQ対応なのかによって、選ぶツールや設計方針も大きく異なります。現場の業務課題と照らし合わせてユースケースを具体化することが、失敗しない導入の第一歩です。
ステップ2:ナレッジ整備と連携設計
チャットボットの応答精度を左右するのが、「ナレッジ」の質と構造です。
FAQや社内マニュアル、手順書など、回答に使う情報を整理し、チャットボットと連携できる形式に整備します。必要に応じて情報の粒度を揃えたり、検索性を高めたりする前処理も重要になります。
ステップ3:PoC(試験導入)で小さく検証
いきなり全社導入するのではなく、まずは限定された部門や業務範囲でPoC(概念実証)を行いましょう。
この段階では、回答の正確性/問い合わせ削減効果/ユーザーの評価といった指標で実用性を検証します。小規模でも成功体験を積むことで、社内理解と導入意欲が高まりやすくなります。
ステップ4:改善サイクルと運用体制の構築
PoCで得た知見をもとに、チャットボットのシナリオやナレッジを改善し、対象範囲を徐々に広げていきます。あわせて、応答ログの分析・メンテナンス・ナレッジ更新の担当体制を明確にし、持続可能な運用設計を構築することがポイントです。
まとめ|生成AIサポートチャットボットで「問い合わせ対応」は次のフェーズへ
生成AIサポートチャットボットは、これまで人の手で対応していた問い合わせやFAQ業務を、よりスムーズかつ高品質に自動化できる有効な手段です。
単なる業務効率化にとどまらず、対応品質の標準化やナレッジ活用の促進といった、企業の「問い合わせ対応のあり方そのもの」をアップデートする力を持っています。
とはいえ、導入にあたっては
- 目的の明確化
- ナレッジの整備
- スモールスタートでの検証
- 社内の活用体制の構築
といった段階的な進め方と、継続的な改善サイクルが欠かせません。
まずはPoCなどの小さな導入から着手し、現場での活用可能性を探るところから始めてみてはいかがでしょうか。
そして、もし導入や社内展開に不安がある場合は、ツール選定から教育までを支援するプロフェッショナルなサポートを活用するのも一つの方法です。
📘生成AIを“現場で使える力”に変える!
ツールの選び方から運用設計・社内教育まで、まるごと支援します。
\ 組織に定着する生成AI導入の進め方を資料で見る /

FAQ(よくある質問)
- Q生成AIサポートチャットボットと、従来型チャットボットの違いは何ですか?
- A
生成AIサポートチャットボットは、ChatGPTなどの生成AIを活用して、質問の文脈や意図を理解しながら自然な回答を生成します。 一方、従来型チャットボットはあらかじめ設定されたルールやシナリオに沿ってしか応答できません。そのため、生成AI型は曖昧な質問にも柔軟に対応でき、定型外の問い合わせにも強いのが特徴です。
- Q生成AIチャットボットは社内業務にも活用できますか?
- A
はい、社内向けのヘルプデスクやFAQ対応にも非常に効果的です。特に情シス・人事・総務などへの繰り返しの質問対応を自動化することで、担当者の工数削減とナレッジの標準化を同時に実現できます。
- Qチャットボットの導入には専門知識が必要ですか?
- A
ツールによりますが、ノーコードで導入できるサービスも多数あります。ただし、ナレッジの整備や運用設計には一定の設計力やAIリテラシーが求められるため、外部の支援を活用する企業も増えています。