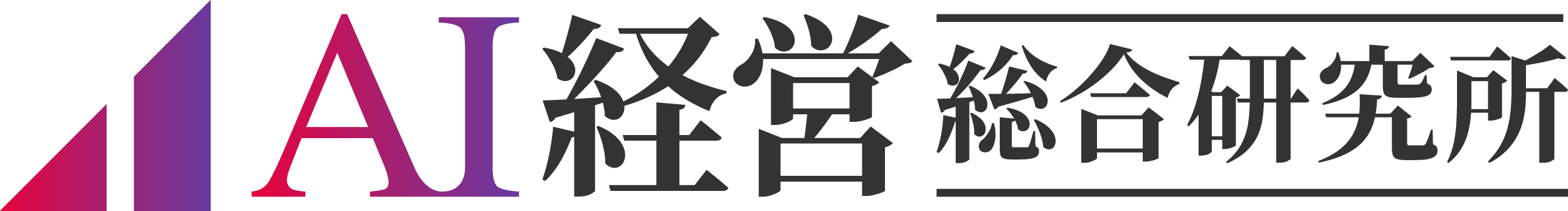ChatGPTをはじめとした生成AIツールの活用が、企業の業務改革を大きく後押ししています。
文章作成や議事録要約、FAQ対応、さらには新しい企画提案の支援まで、その活用範囲は急速に広がっています。
とはいえ──
「実際に他社はどんなツールを導入しているのか?」
「導入して、どんな業務に活かしているのか?」
「うちの会社でも使えるイメージが持てない…」
こうした疑問や不安を持つ企業担当者の方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、国内企業による生成AIツールの導入事例を35社分、業種別に整理して紹介します。
あわせて、導入企業がどのように活用定着を進めているのか、その成功の背景や課題、よくあるつまずきポイントも解説します。
- 今後、自社での導入や社内展開を検討している方
- 生成AI研修やリテラシー向上が必要だと感じている方
- 上司や経営層に導入の説得材料を探している方
こんな方にとって、導入のヒントや実践アイデアが詰まった内容になっています。
ぜひ最後までご覧いただき、自社の生成AI活用にお役立てください。
\ 組織に定着する生成AI導入の進め方を資料で見る /
生成AIの導入が企業にもたらす3つのインパクト
生成AIは、単なる「効率化ツール」ではありません。
実際に導入した企業の事例を分析すると、業務の質・スピード・組織の在り方そのものに影響を与えていることがわかります。
ここでは、企業が生成AIを導入することで得られる代表的なインパクトを3つご紹介します。
①生産性の圧倒的向上
議事録の自動生成、契約書のドラフト作成、メール返信文の生成など、時間を取られがちなルーチン業務が大幅に短縮されます。
例えば、MicrosoftCopilotを導入した企業では、「報告書作成にかかる時間を5分の1に削減」「議事録の作成工数を80%カット」など、定量的な改善が報告されています。
生成AIは、単なる時短ではなく、「本来集中すべきコア業務に時間を戻す」手段として注目されています。
②社員の発想力・創造性の解放
生成AIは、過去のパターンをもとに案を出すことが得意です。
そのため、企画・マーケティング・クリエイティブ分野では、「ゼロから考える」苦労が軽減され、発想の幅が広がるという声が多く上がっています。
たとえば、大手小売企業では、AIが生成した接客トーク案をもとに現場スタッフがブラッシュアップすることで、顧客満足度が向上。
“人にしかできない価値”を引き出すパートナーとして機能しています。
③情報格差・属人化の解消
生成AIは、誰でも同じように情報を引き出し、使えることが特長です。
これにより、「詳しい人しか使えない」「担当者がいないと進まない」といった属人化の課題を組織全体で平準化することが可能です。
実際に、ある自治体では、政策文書の下書きを生成AIが支援することで、職員間の文章力の差を補完し、全体の業務品質が安定したという事例もあります。
これら3つのインパクトは、ツールの選定だけでなく、導入時の目的設定や活用設計が明確になっているかによって成果が左右されます。
関連記事:AI導入後のつまずきを防ぐには?生成AI活用を定着させるフォローアップ施策5選
なぜ企業は生成AI導入を急ぐのか?3つの背景
生成AIの導入は、単なる流行ではなく、企業が直面している構造的な課題に対する解決策として注目を集めています。
ここでは、導入を急ぐ企業が増えている背景を3つに分けて整理します。
人手不足と生産性向上ニーズ
少子高齢化に伴い、多くの業界で慢性的な人手不足が課題となっています。
採用が難しい中で、「限られた人数でどう業務を回すか」が経営上の重要テーマです。
こうした状況で、議事録作成や報告書作成、マニュアル整備といった**“時間はかかるが付加価値が低い業務”**を自動化できる生成AIが、強力な武器として注目されています。
たとえば、議事録生成にかかる時間を80%削減した事例や、月間数百件の文書作成をAIで置き換えた例も登場しており、即効性ある生産性向上手段としての期待が高まっています。
ナレッジ属人化の解消
「詳しい人がいないと仕事が進まない」「ベテランの知識が暗黙知のまま」という状況は、多くの組織が抱える共通の悩みです。
生成AIは、社内ナレッジをベースに回答するチャットボットやFAQ生成ツールとして活用することで、誰でも情報にアクセスできる環境をつくることができます。
たとえば、大手金融機関が構築した「ナレッジボット」は、新人や異動者でもベテランと同じ水準で業務をこなせるよう支援しており、教育コストの削減や品質の平準化にもつながっています。
生成AIの進化と費用対効果
2023年以降、ChatGPTやCopilotをはじめとした生成AIツールは劇的に進化し、実務レベルで十分に活用できる性能と安定性を備えるようになってきました。
加えて、クラウド経由でのAPI提供や法人向けサービスの整備が進み、「小さく始めて成果を出しやすい環境」が整いつつあります。
さらに、価格帯も柔軟で、1人あたり月数千円から始められるツールも多く、コストパフォーマンスの高さも導入を後押ししています。
「PoC(試験導入)→効果検証→本格導入」といった段階的な展開も可能であり、中堅・中小企業にとっても現実的な選択肢となっています。
【業種別】生成AIツールを導入している企業事例35選
生成AIツールを導入している企業は年々増加していますが、その活用方法や導入体制は業種によって大きく異なります。
業務特性やセキュリティ要件、現場のニーズに応じて、選ばれるツールや導入のアプローチにも個性が出ているのが実情です。
そこで本章では、ChatGPTやCopilotをはじめとする生成AIツールの導入事例を、以下のように業種別に35社厳選してご紹介します。
| 業種名 | 企業名(導入企業例) | 導入ツール例 |
| 製造業 | ・日立製作所 ・富士通 ・川崎重工業 | ChatGPTAPI(Azure)、GitHubCopilot、独自AI |
| 金融・保険 | ・三菱UFJ銀行 ・SOMPOホールディングス ・みずほフィナンシャルグループ | AzureOpenAI(GPT-4)、音声認識API、社内ナレッジBot |
| 流通・小売 | ・セブン&アイHD ・大丸松坂屋百貨店 ・良品計画(無印良品) | ChatGPTAPI、独自生成AI、GoogleVertexAI |
| IT・通信 | ・ソフトバンク ・NTTデータ ・KDDI ・サイバーエージェント | BizAIChat、AzureOpenAI、GPT搭載社内アプリ |
| 自治体・教育機関 | ・横須賀市 ・福岡県庁 ・東京都教育委員会 ・金沢大学 | ChatGPTAPI(Azure)、独自生成AI、Copilot |
それぞれの企業がどんなツールをどう使い、どのような成果を上げているのか――。
「自社の参考になるのはどこか?」という視点で読み進めていただくことで、導入のヒントがきっと見つかるはずです。
製造業の導入事例一覧
| 企業名 | 導入ツール | 活用内容 | 成果・特徴 |
| 日立製作所 | ChatGPTAPI(Azure経由) | 議事録・設計書作成支援 | 全社員向けAIポータル開発、利用者の8割が効果実感 |
| 富士通 | Copilot(GitHub/M365) | ソースコード/技術文書の作成支援 | 社内ポリシー+研修を整備、段階的に展開 |
| 川崎重工業 | 独自AI+OpenAIAPI | 技術マニュアル自動生成/社内Q&A | ドキュメント作成時間70%削減 |
製造業の傾向と注目ポイント
製造業では、ドキュメント作成や設計レビュー、プログラミング支援といった「専門知識×反復業務」への活用が進んでいます。
特に日立製作所のように、全社レベルでプロンプト共有や活用ナレッジを整備する動きは、他業界にも応用可能な成功事例といえるでしょう。
また、「精度が求められる業務」ほど、ツール選定と社内教育がカギを握ります。単なる試験導入ではなく、運用設計をセットにした“本格導入”が主流になりつつあります。
金融・保険業の導入事例一覧
| 企業名 | 導入ツール | 活用内容 | 成果・特徴 |
| 三菱UFJ銀行 | AzureOpenAI(GPT-4) | 議事録・文書要約 | 業務時間30%削減、リスク部門と連携したルール整備 |
| SOMPOホールディングス | 独自生成AI+音声認識API | 通話要約/対応記録自動生成 | 作成業務70%削減、オペレーターの品質向上と負荷軽減 |
| みずほFG | 独自ナレッジボット(社内DB連携) | 社内Q&A・マニュアル検索 | 検索時間40%短縮、新人の業務定着スピード向上 |
金融・保険業の傾向と注目ポイント
金融機関では、機密性が高い文書や業務ノウハウを効率的に扱う手段として、生成AIの価値が再評価されています。
セキュリティ要件が厳しい分、「Azure経由のGPT」や「社内開発のナレッジボット」など、閉域環境+専用設計での導入が目立ちます。
また、SOMPOのように、音声からの要約自動化にまでAIを活用する動きは、CS部門やコールセンターを抱える他業界にも応用可能です。
いずれも共通して、ルール整備・教育・効果測定までを含めた“定着設計”が、成功に不可欠となっています。
流通・小売業の導入事例一覧
| 企業名 | 導入ツール | 活用内容 | 成果・特徴 |
| セブン&アイHD | ChatGPTAPI+社内開発AI | 商品発注業務の最適化 | 発注作業時間を10分の1に短縮、4割の廃棄削減 |
| 大丸松坂屋百貨店 | 独自開発の生成AI+社内接客データ | 接客スクリプトの自動生成 | スタッフの接客力向上、顧客満足度向上に寄与 |
| 良品計画(無印良品) | GoogleCloudVertexAI | 商品企画案・アイデアの生成支援 | 商品開発サイクルの短縮、部門間のアイデア共有を促進 |
流通・小売業の傾向と注目ポイント
小売業界では、接客品質の向上や発注業務の効率化といった、現場に密着した業務改善への活用が顕著です。
特にセブン&アイの事例では、店舗スタッフでも直感的に使えるAIUIの開発と、精度向上のための継続的フィードバック運用が成功の要因とされています。
大丸松坂屋では、AIが生成した接客スクリプトを活用することで、非ベテランでも“プロ品質”の応対ができる体制を実現。これは人手不足・教育時間の短縮にもつながる重要な成果です。
また、無印良品のように、商品企画やアイデア出しの段階からAIを活用する企業も増えており、生成AIは「現場の支援」から「価値創造」へと領域を広げつつあります。
IT・通信業の導入事例一覧
| 企業名 | 導入ツール | 活用内容 | 成果・特徴 |
| ソフトバンク | 独自開発AI「BizAIChat」+GPTAPI | 社内チャット業務支援・FAQ生成 | 月1万件以上の利用、部門横断で活用ナレッジを共有 |
| NTTデータ | MicrosoftAzureOpenAI+社内環境 | FAQ生成、提案書作成支援 | 社内知識の活用を加速、生成物の品質ガイドラインも整備 |
| KDDI | GPTベースの対話型AI(社内アプリ) | 社内手続き・マニュアル検索 | 月間利用率90%以上、問い合わせ時間を半分以下に削減 |
| サイバーエージェント | OpenAIGPT-4API | 広告コピーの草案生成、企画アイデア支援 | 制作時間短縮+若手社員のアウトプット品質が向上 |
IT・通信業の傾向と注目ポイント
IT・通信業界では、生成AIを社内情報の活用基盤として位置づける動きが加速しています。
特に、ソフトバンクやNTTデータのように、“部門横断的に使える社内AIチャット”を開発し、全社に展開する事例が増加中です。
共通するのは、使うだけでなく“育てるAI”として、利用部門ごとのナレッジやプロンプトを継続的に蓄積していること。
KDDIのように、社内手続きのQ&Aやマニュアルを即時検索できるようにすることで、バックオフィスの問合せ対応時間を半減するなど、**「社内ヘルプデスクの代替」**としての導入も進んでいます。
また、サイバーエージェントでは、広告コピーやキャンペーン企画の“たたき台”生成に生成AIを活用することで、新人や非専門人材でも提案の初期案を高速で出せる体制を構築。
このように、IT企業ならではの柔軟性と実装スピードを活かし、生成AIの効果を最速で可視化する姿勢が特徴です。
自治体・教育機関の導入事例一覧
| 団体・機関名 | 導入ツール | 活用内容 | 成果・特徴 |
| 横須賀市 | ChatGPTAPI(Azure経由) | 政策文書・答弁案の草案作成支援 | 国内自治体で初導入、業務時間を約60%削減 |
| 福岡県庁 | 独自開発の生成AIシステム | 庁内文書の要約、他自治体事例の収集支援 | 文章作成負荷を軽減、全庁横断で運用 |
| 東京都教育委員会 | MicrosoftCopilot | 教職員の業務補助(文書作成・通知文作成) | 試験導入で教員の事務負担を20~30%削減 |
| 金沢大学 | 独自チャットAI+学習支援ツール | レポート構成の支援、FAQ対応 | 学生の質問対応を自動化し、教職員の負担を軽減 |
自治体・教育機関の傾向と注目ポイント
自治体・教育分野では、文書作成の効率化や知識共有の迅速化が生成AIの主な活用目的となっています。
先駆者である横須賀市では、ChatGPTAPIを利用した庁内検証により、職員の答弁案や文書の草案作成において大幅な時間短縮を実現。この成功が他自治体への導入拡大のモデルケースとなっています。
福岡県のように、全庁横断での活用・事例共有を行うことで、AIの精度と実用性を向上させており、「自治体=慎重」というイメージを覆すスピード感ある導入が注目されています。
また、教育機関でも、東京都教育委員会や金沢大学のように、生成AIを教員や学生の“アシスタント”として活用する事例が登場。
教職員の事務負担軽減だけでなく、学生の学習支援・個別対応の効率化にもつながっており、今後の広がりが期待されます。
\ 組織に定着する生成AI導入の進め方を資料で見る /
企業が導入している代表的な生成AIツール一覧
生成AIの導入を進める企業が増える中、活用されているツールの種類も年々多様化しています。
「ChatGPT以外に、どんなツールが使われているのか?」「自社にはどのツールが合っているのか?」と気になっている方も多いのではないでしょうか。
このセクションでは、実際に導入が進んでいる代表的な生成AIツールを、特徴や用途別に整理してご紹介します。
ChatGPT(OpenAI)
言わずと知れた生成AIの代表格。自然な対話形式で、文章生成、要約、翻訳、議事録作成、アイデア出しなど、あらゆる業務に対応できる汎用性が強みです。
API連携によって社内ポータルや独自チャットボットに組み込む企業も多く、活用の自由度が高いのが特徴です。
MicrosoftCopilot(M365/GitHub)
Microsoft製品と深く統合されたCopilotシリーズは、セキュリティやガバナンス要件が厳しい大企業や金融機関でも導入しやすいのが魅力です。
WordやExcel、Outlook上での文書作成やメール下書き、GitHubCopilotによるコーディング補助など、日常業務への自然な組み込みが可能です。
Claude(Anthropic)
ChatGPTと並び注目される対話型AI。長文への対応力が高く、日本語でも自然で読みやすい出力が得られると評価されています。
リスクへの慎重な姿勢(憲法的AI原則)もあり、社内文書や議事録要約への活用が進んでいます。
GoogleGemini(旧Bard)
GoogleWorkspaceとの親和性が高く、Gmailやスプレッドシートとの連携が可能。
検索感覚で使えるチャットAIとして、リサーチ業務や社内の情報整理に活用されるケースが多いです。
NotionAI/MiroAIなど
ドキュメント作成やホワイトボード型ツールにAIを組み込んだタイプ。
NotionAIは「議事録の要約」や「構成案の作成」など、情報整理やナレッジ共有業務に強みがあります。
MiroAIは会議中のアイデア整理やロジックマップ生成に活用されることが多く、DX推進部門で導入が進んでいます。
国産ツール(ELYZA/Liny/PKSHAChatbotなど)
特に日本語の正確性や業務特化の安心感を重視する企業では、国産ツールの導入が進んでいます。
- ELYZA:要約生成が強み。議事録やレポートの圧縮に活用。
- Liny:LINE連携可能な顧客対応チャットAI。
- PKSHAChatbot:FAQ自動生成やナレッジベース整備を支援。公共機関や金融機関での導入実績もあり。
その他注目ツール(ZapierAI/Adept/Perplexityなど)
自動化やWebリサーチに特化した新興ツールも続々と登場しています。
- ZapierAI:複数ツールを連携し業務フローを自動化
- Adept:操作画面を読み取って自動でタスク実行
- PerplexityAI:高精度の出典付きリサーチ特化型AI
ツール選定の視点:「用途×安全性」で見極めを
ツールごとに得意分野やセキュリティ要件、導入コストは大きく異なります。
以下のような視点で、自社に適したツールを見極めることが重要です。
- どんな業務に活用したいか?(要約/生成/検索)
- クラウドかオンプレか、セキュリティ要件は?
- 社内展開しやすいUIや操作性か?
関連記事:【2025年最新】法人向け生成AIツール12選|セキュリティ・定着・管理機能で徹底比較
導入企業はなぜ成果を出せたのか?共通する3つの成功パターン
生成AIの導入は、ツールを導入するだけでは成果に直結しません。
実際に成果を上げている企業には、「ただ導入した」ではなく、「使いこなす環境を整えている」という共通点があります。
ここでは、企業が生成AIを業務に定着させ、実際に成果を出すために実践している3つの成功パターンをご紹介します。
①スモールスタートで効果を可視化する
多くの成功企業は、最初から全社導入するのではなく、特定部門や業務で小さく始めています。
たとえば、NTTデータでは営業資料の作成支援から導入を開始し、改善効果を検証しながら徐々に他部門へ展開しました。
このように、「まずやってみる」「数値で効果を示す」ことが、社内説得や全社展開の足がかりになるのです。
②現場主導で“使いやすさ”を重視する
導入を主導しているのが情報システム部門やDX推進室であっても、実際に使うのは現場の社員です。
現場が使いやすいように、以下のような工夫を行っている企業が成果を上げています。
- UIがわかりやすい社内チャットツールと連携
- よく使うプロンプトのテンプレートを共有
- 「AIを使うと何が楽になるか」を具体例で教育
たとえば、ソフトバンクでは「BizAIChat」の利用部門ごとに、よく使うプロンプト集やFAQナレッジを整備。これが定着率を高める決め手となりました。
③社内教育とルール整備をセットで行う
成果を出している企業の多くは、ツールの導入と同時に「社内教育」と「利用ルールの整備」にも力を入れています。
たとえば、
- 三菱UFJ銀行では、社内での利用ガイドラインと「誤生成を防ぐための使い方講座」を整備
- 大手メーカーでは、生成AIリテラシー研修を部門ごとに実施し、社内の不安を払拭
このように、生成AIを使いこなせる人材・組織づくりが、導入後の活用レベルに直結するのです。
\ 組織に定着する生成AI導入の進め方を資料で見る /
よくある導入の課題とその乗り越え方
生成AIの導入に前向きな企業が増える一方で、実際の現場では次のような悩みや懸念も多く聞かれます。
ここでは、企業が直面しやすい導入の課題と、それに対する具体的な乗り越え方をご紹介します。
課題①:社員のAIリテラシーに差がありすぎる
「一部の社員しか使いこなせない」「現場で敬遠されてしまう」といった声は少なくありません。
解決策
- 段階的な研修プログラムの導入(初級→応用)
- 実務に直結したプロンプトのテンプレートを配布
- 「できる人」が周囲をサポートする“社内AIサポーター制度”
📌事例:某自治体では、職員向けの「1時間研修×業務別ハンズオン」を実施し、AI活用率が2倍以上に向上。
課題②:情報漏洩や誤生成への不安が消えない
生成AIは便利な反面、「社外秘の情報をうっかり入れてしまうのでは」「出力が正しいか判断できない」といった懸念も根強くあります。
解決策
- セキュリティ要件を満たすツール(CopilotやAzureGPT)を選定
- 社内利用ポリシー・禁止事項・誤生成チェックリストを明文化
- 出力内容の二重チェックをルール化
📌事例:金融業界では、閉域ネットワークでの運用+マニュアル教育により、安心して全社展開が進んでいます。
課題③:どの業務から始めればいいかわからない
AIの可能性は広すぎて、「どこから着手すべきか迷う」ことも多いです。
解決策
- 他社事例を参考に「議事録作成」「マニュアル要約」など成果が出やすい業務からスタート
- PoC(試験導入)で小さく始め、効果が出た業務を軸に展開
- 利用頻度・工数削減効果が大きい業務に絞る
📌事例:ある小売企業では、まずは商品説明文の生成から始め、社内理解を得たうえで接客業務に拡張しました。
導入時の不安を解消するには「環境整備と伴走支援」がカギ
生成AIを定着させるには、ツールだけでなく、人・ルール・習慣の整備が欠かせません。
AIを使いこなす組織をつくるには、最初の一歩=社内教育と仕組みづくりが最も重要なのです。
自社でも導入するには?まずは「使いこなせる人材づくり」から
ここまでご紹介してきた通り、生成AIはすでに多くの企業で導入が進み、
議事録や提案書の作成、接客対応、商品企画まで幅広い業務で成果を上げています。
一方で、それらの企業が共通して実践しているのは、単にツールを導入するだけではなく、
「使いこなせる人材と体制」を整備しているという点です。
「導入したけど、現場が使ってくれない」を防ぐには?
ツールそのものよりも重要なのが、使い方を理解し、業務に定着させられる人材の育成です。
- 部署ごとに活用の幅や悩みが違う
- 最初の数ヶ月で社内の温度差が生まれやすい
- 活用事例やナレッジが属人化しがち
こうした壁を乗り越えるには、目的に沿った研修や導入支援が必要不可欠です。
AI経営総合研究所では、企業向けの生成AI研修をご提供しています
私たちは、企業の業務や体制に合わせて、実践型の生成AI研修をカスタマイズ提供しています。
- 業種・部門ごとの業務フローに沿った研修設計
- ツールの使い方だけでなく、「活用の考え方」から支援
- 社内で継続的に展開できるテンプレ・教材も提供
\ 組織に定着する生成AI導入の進め方を資料で見る /
まとめ|生成AI導入の鍵は「ツール×人材×定着環境」
生成AIは今や、多くの企業が本格導入を進める業務改革の新常識となりつつあります。
本記事では、実際に導入して成果を出している企業の事例から、以下のポイントを紹介しました。
- 企業が導入している代表的な生成AIツール一覧
- 導入が進む35社の具体的な活用事例
- 成功する企業に共通する3つのパターン
- よくある導入の課題とその解決策
いずれの企業も共通しているのは、「使いこなせる人材」と「現場で活きる活用ルール」を整えていることです。
「自社でもそろそろ生成AIを本格導入したい」
「まずは現場が抵抗なく使える環境を整えたい」
そうお考えの方は、社内向けの教育やガイドライン整備から始めるのが成功の近道です。
\ 組織に定着する生成AI導入の進め方を資料で見る /
- Q生成AIの導入はどの部署から始めるのが良いですか?
- A
最も効果が見えやすく、業務が定型化されている部署(例:営業、企画、人事など)から始めるのが効果的です。
まずは議事録や資料作成などのシーンで導入し、成果を可視化することで、社内展開がスムーズになります。
- Q社員のITリテラシーはバラバラですが、使いこなせるでしょうか?
- A
大丈夫です。初級者向けの研修や、業務に沿ったテンプレートの活用などで段階的に習得できます。
「まずは使ってみる」環境を整えることで、スキル差を埋めつつ定着を図れます。
- QChatGPTなどの外部ツールを使うと情報漏洩が不安です。
- A
セキュリティ要件を満たす法人向け生成AI(例:MicrosoftCopilot、AzureGPTなど)を使うことで、
データの取り扱いに配慮しながら活用できます。加えて、利用ルールの整備も不可欠です。
- Q社内展開にあたって必要な準備は?
- A
以下の3つが基本です。
- ツールの選定(目的に合うもの)
- 利用ルールの整備(禁止事項・誤生成対策)
- 社員向けの研修・教育(初期定着支援)
これらをワンセットで準備できれば、スムーズな全社展開が可能になります。
- Q研修や導入支援にはどれくらいの費用がかかりますか?
- A
ご希望の内容や対象人数により変動しますが、まずは無料で資料をご覧いただけます。
費用の目安やカスタマイズ例も記載していますので、以下からご確認ください。
\ 組織に定着する生成AI導入の進め方を資料で見る /