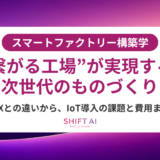ChatGPTやCopilotなどの生成AIを導入し、社内研修も実施済み。
一見、社内のAI活用が順調に進んでいるように見える企業でも──
「結局、使っているのは一部の社員だけ」
「研修のときは盛り上がったけど、実務では話題にも出ない」
「OJTでどう育成すればいいか分からない」
という声が後を絶ちません。
多くの企業が見落としているのが、「集合研修のあと、実務にどう定着させるか」という視点。つまり、OJTの中でAI活用を“当たり前の習慣”として根づかせる設計が欠けているのです。
この記事では、AIを“使える力”として現場に定着させるためのOJT設計について、実践的なステップとチェックリストを交えながら解説します。生成AIを「研修で終わらせない」ために、現場の育成をどう変えるべきか。
そのヒントを、あなたの会社のOJTに落とし込んでいきましょう。
研修については以下の記事もおすすめです!
▶︎ AI研修が“1回きり”で終わってしまいやすい理由とは?現場に定着させる「継続の仕組み」を解説
▶︎ 研修が定着しないのは“忘却前提”がないから?再接触設計×生成AIで行動に変える方法
▶︎ 研修しても人が育たない職場の特徴|“やりっぱなし教育”を脱する5つの処方箋
【無料資料】なぜ?AIが社内で使われない本当の理由ツールを導入しただけではAI活用は進みません。2,500社の支援で見えた、成功企業に共通する「3つの秘訣」をまとめた資料で、貴社の次の打ち手を見つけませんか?
▶︎ 詳しい内容を確認する!
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
なぜAIは定着しない?研修→実務の“空白地帯”が生む3つのズレ
多くの企業で、「AI研修はやったが、現場ではほとんど使われていない」というギャップが生まれています。
その背景には、研修から実務への“つなぎ目”が設計されていない、いわば「空白地帯」の存在があります。
ここでは、AI活用が現場で定着しない理由として、特に多く見られる3つのズレを整理します。
① 研修と現場業務がつながっていない
研修で紹介されたAIツールの使い方が、現場で直面する業務とリンクしていないケースがよくあります。
「ChatGPTで文章を要約できる」「アイデアを出せる」といったスキルは学んだとしても、それをどの業務で、どのタイミングで使うのかが曖昧だと、結局“研修止まり”になってしまいます。
✅【ポイント】
「どの業務で使えばよいか」が明文化されていないと、活用は進まない。
② OJTを担う上司自身がAIに不慣れ
OJTにおいて、部下の育成を担うのは多くの場合その上司ですが、上司もAI活用に不安を抱えているというケースが少なくありません。
- 「自分も使いこなせていないのに、教えるなんて無理」
- 「失敗例を見せたら恥ずかしい」
- 「使い方を聞かれても答えられないかも…」
こうした心理的ハードルが、現場でのAI定着を妨げています。
✅【ポイント】
「教える側のリテラシー支援」もOJT設計の一部と捉える必要があります。
③ 「間違えてはいけない」という空気が、AI活用を遠ざける
生成AIは万能ではなく、当然ながら誤りもあります。
しかし、AI活用に対する“完璧主義”が根強い現場では、ミスを恐れて使わなくなる傾向があります。
- 「AIの回答が間違っていたらどうしよう」
- 「使って失敗したら評価が下がるかも」
- 「ツールに頼るのは“手を抜いている”と思われるのでは」
こうした空気感が、「まずは使ってみよう」という挑戦を阻みます。
✅【ポイント】
AI活用には“失敗しても大丈夫”な土壌づくりが必要です。
このようなズレを放置すると、せっかくの研修が無駄になってしまうだけでなく、「AIは現場では役に立たない」という誤解が定着してしまいます。
AIをOJTで“使える力”に変えるための4ステップ
研修で学んだ内容を、現場で「実際に使える力」に変えるためには、OJTにおける仕組み設計が必要不可欠です。
ここでは、AI活用を自然に業務へ定着させていくための4つの実践ステップをご紹介します。
① 「この業務で使う」を明確にする|トリガーを設計する
まずは、どの業務でAIを使うかを具体的に決めておくことが重要です。
OJTの中で「迷ったときはこの業務で試してみよう」という“トリガー”となる場面を設定しましょう。
- 資料作成時のたたき台作成にChatGPTを使う
- 社内共有文の要点整理にCopilotを使う
- 顧客対応メールの文案ドラフトに生成AIを活用する
✅【ポイント】
「使うかどうかを都度考える」のではなく、「この業務では使う」と決め打ちにすることで、行動に落とし込みやすくなります。
② 上司や育成者が“一緒に使う”|見せて、話して、促す
「教える」よりも効果的なのが、「一緒に使ってみせる」ことです。
たとえば、1on1や打ち合わせの場で、育成者自身が実際にChatGPTを立ち上げてプロンプトを考える様子を見せることで、現場のAI活用は加速します。
- 「こんな聞き方したら、精度が上がるんだね」
- 「ちょっと試してみようか」
- 「今のやり取り、プロンプトにして残しておこう」
このような言動が、部下にとって“使っていい空気”をつくります。
✅【ポイント】
完璧でなくてもいい。「使っている姿」を見せること自体が育成につながる。
③ 小さな成功体験を積ませる|“使ってラクだった”を実感させる
AI活用が定着するかどうかは、「ラクになった」というポジティブな体験の蓄積にかかっています。
最初は、5分の時短や、資料の質が少し良くなったといった小さな成功で十分です。
- 「前よりスムーズに書けた」
- 「情報収集の時間が減った」
- 「プロンプトの工夫で精度が上がった」
こうした体験を「たまたま」ではなく、意図して設計することが大切です。
✅【ポイント】
成果を実感させることが、継続的な活用につながります。
④ 活用を“共有資産”にする|プロンプト・Tipsの見える化
最後に、個人の学びや工夫を、チーム全体で共有する仕組みを整えましょう。
- Slackに「プロンプト共有チャンネル」を設ける
- 社内ポータルに「今週の活用Tips」を投稿
- 小さな成功を朝会などで共有する時間をつくる
このように、活用のノウハウが自然と循環する文化を育てていくことが、OJTを通じたAI活用定着のカギです。
✅【ポイント】
「誰が使っているか分からない」状態をなくし、“みんなで育てるAI活用”にすることが理想です。
【無料資料】AI導入を成功に導く「5段階ロードマップ」AI導入、何から始めるべきかお悩みですか?2,500社の支援実績から導き出した、経営層の巻き込みから文化形成までを網羅した「5段階の成功ロードマップ」を今すぐご覧ください。
▶︎ 詳しい内容を確認する!
AI OJTを成功させるための実践チェックリスト
ここまでご紹介した4ステップを、自社のOJTに取り入れる準備ができているかどうか。
以下のチェックリストで、自社のOJTがAI活用に対応できる設計になっているかを確認してみましょう。
| チェック項目 | 状況 |
| OJTの中で「AIを使う業務」が具体的に明示されている | □できている □一部できている □できていない |
| 上司や育成者がAIを使う様子を、実際に部下に見せている | □できている □一部できている □できていない |
| AIを活用した結果、「作業時間短縮」や「資料の質向上」などの成功体験が部下に共有されている | □できている □一部できている □できていない |
| Slackや社内ポータルなどに「プロンプト事例」や「活用Tips」を投稿・共有している | □できている □一部できている □できていない |
✅ ひとつでも「できていない」があれば、OJTの設計を見直すチャンスです。
単発の研修だけでは、現場のAI活用は定着しません。
日常業務の中で、AIを“使って当たり前”の状態にするための育成設計が求められています。
\ 組織に定着する生成AI導入の進め方を資料で見る /
成功するOJT設計のポイント|よくある落とし穴を避けるには?
「AI活用をOJTに組み込む」と言っても、ただ現場に任せるだけでは定着は難しいのが実情です。
ここでは、AI OJT設計でよくある失敗と、それを避けるためのポイントを整理します。
✔ 「OJT任せ」で丸投げしない
よくある失敗は、「研修は終わったから、あとは現場でOJTでやってね」と丸投げしてしまうことです。
現場の上司が「何をどう教えたらいいのか分からない」まま進めると、結局誰も使わない状況に逆戻りします。
✅【対策】
OJTにも“設計”が必要。「誰が」「何を」「どう教えるか」の流れをガイドラインで明示する。
✔ 上司=教える人、の前提を疑う
AI活用に関しては、必ずしも上司が“先生”である必要はありません。
むしろ、「部下と一緒に試す」「チームで探究する」ような共創型の学び方のほうが、組織としての定着力が高まります。
✅【対策】
「上司が詳しくなくても進められる」プロンプト例や活用パターンをテンプレ化して共有する。
✔ 成功体験は“見える化”して広げる
せっかくAIを使ってうまくいったとしても、それが共有されないと「活用ノウハウ」は個人の中に閉じてしまいます。
これでは組織に知見がたまりません。
✅【対策】
成果は「小さな成功」で十分。Slackや朝会で共有する習慣を仕掛けることが、心理的ハードルの解消にもつながります。
OJTの設計においては、“人材育成”と“仕組み設計”の両面が欠かせません。
属人的な指導ではなく、チームでAI活用を育てる文化を目指すことが、真の意味での「AI人材の定着」につながります。
OJTでのAI活用を支援する「外部パートナー」の使い方
AIをOJTに組み込もうとすると、「そもそも教えられる人がいない」という壁に直面する企業は少なくありません。
上司も初学者、現場は手一杯、情報システム部門は支援の限界…。そんな時にこそ検討すべきなのが、外部パートナーの活用です。
「使い方を教える研修」だけでは不十分
多くのAI研修が提供しているのは、あくまで「ツールの使い方」です。
しかし、OJTの中で求められるのはそれだけではありません。
- 現場業務にどう組み込むかの設計支援
- プロンプトや活用シーンのテンプレート化
- 教える側・教わる側のリテラシーギャップを埋める支援
これらを“研修で終わらせず、継続的に伴走できるパートナー”かどうかが、外部サービス選定の分かれ目です。
SHIFT AIでは、OJTと連動した「定着支援型AI研修」を提供
SHIFT AIでは、以下のようなOJT現場への定着を前提とした研修プログラムを提供しています。
- 各部門の業務内容に応じたAI活用パターンの提案
- 上司・OJT指導者向けの「伝え方サポート」
- 「この業務ではこのプロンプトを使う」という現場向けツールキットの提供
- 活用度合いの可視化・フィードバック設計まで一括支援
OJTと連動するからこそ、“やって終わり”ではない研修が実現します。
\ 組織に定着する生成AI導入の進め方を資料で見る /

FAQ|よくある質問
- Q上司がAIに詳しくなくても、OJTで教えられますか?
- A
はい、教える側が“完璧である必要”はありません。
プロンプト例や活用シーンのテンプレートがあれば、「一緒に使ってみる」ことでOJTは機能します。むしろ、部下と一緒に試行錯誤するスタイルのほうが、現場には定着しやすい傾向があります。
- QAIをOJTで使わせるには、どの業務から始めればよいですか?
- A
成果が目に見える“定型業務”から始めるのがおすすめです。
たとえば、資料作成、社内報告文、議事録要約、FAQ作成など。初期段階では、業務の一部だけでもAIに任せることで、「使ったらラクになった」という実感を得やすくなります。
- Q少人数のチームでも、OJT型AI活用は可能ですか?
- A
はい、むしろ少人数のほうが柔軟にスモールスタートしやすいです。
AI活用の範囲を限定し、1〜2人で試してから横展開する“PoC(実証導入)型”の進め方が効果的です。SHIFT AIの研修でも、このようなスモールスタート支援が可能です。
- QそもそもOJTにAI活用を組み込むべき理由は?
- A
単発の研修だけでは、現場でAIが“使われる状態”にはなりづらいからです。
OJTを通じて「実務でどのように使うか」を習慣化させることで、AI活用が一部の人だけのものにならず、組織としての定着が進みます。