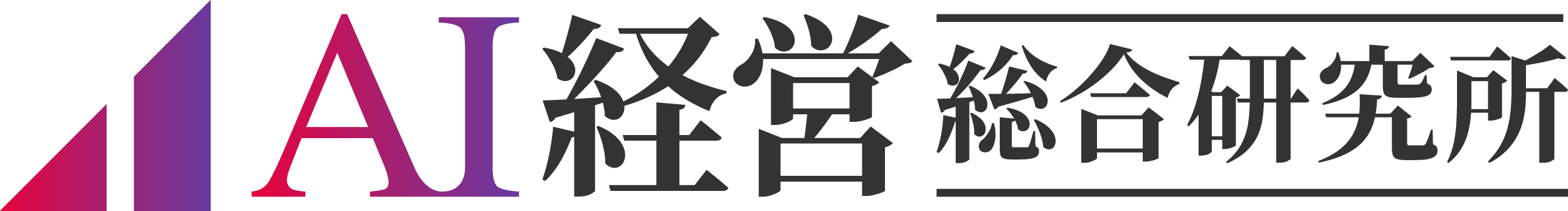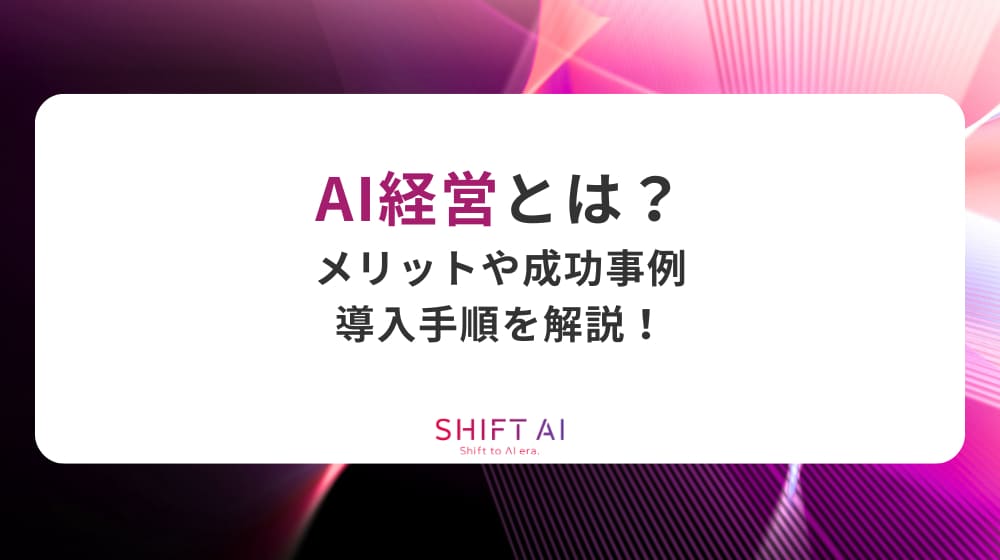近年、AIの進化は目覚ましく、さまざまな企業で導入が進んでいます。AIを活用することで、業務効率化やコストカット、従業員の労働時間短縮などさまざまなメリットがあります。
しかし、「AIをどう自社で活用すればいいかわからない」「そもそもAIを活用できる業務や導入方法がわからない」と感じる方もいるでしょう。
そこで、本記事では、AI経営の基本的な概念をはじめ、活用が進む背景やメリット、導入の具体的な手順、注意点について詳しく解説します。実際に成功を収めた事例もあわせて紹介するので、会社経営を効率化したい方はぜひ参考にしてください。
SHIFT AIではAI経営に関する相談を無料で受け付けています。AIを使った会社経営の方法やAIの導入方法など、幅広いお悩みを相談可能です。AI経営に興味がある、AIの活用を検討している、という方はお気軽にご相談ください。
\ 組織に定着する生成AI導入の進め方を資料で見る /
AI経営とは?

AI経営とは、企業の経営にAIを取り入れることです。経営層の意思決定や従業員の業務を補助する役割としてAIを導入します。AIは幅広い業務に活用でき、日々の業務負担の軽減につながるでしょう。一部の業務では完全に代替することも可能です。例えば、画像生成やWeb上での簡単な問合せ対応など、AIが得意とする分野では、迅速かつ正確な処理が行えます。
AI経営を行うことで煩雑な業務が減り、従業員がより優先度の高い業務に集中できる環境が整うでしょう。また、AIが業務を補助するおかげで、雇う従業員の人数を減らせるため、コストカットや労働力不足の解消も期待できます。
このように、AI経営は企業にとって競争力を高めるための重要な手段となりつつあるのです。
AI経営が注目される背景

AI経営が注目される背景には、主に業務効率化、労働力不足の解消、データ活用などの複合的な要因があります。
現在、AIは業務効率化を目的にさまざまな分野で活用が進んでいます。例えば、ChatGPTを搭載したチャットボットによる問合せ対応や、画像生成AIを活用した広告バナーの作成など、これまで人手で行っていた簡単な業務をAIが代替できるようになっています。また、AI技術の発展に伴い、AIが補完できる業務範囲は広くなり、アウトプットの質も向上するでしょう。そのため、多くの企業がAIの導入を前向きに検討しているのです。
次に、労働力不足の解消もAI経営の注目ポイントの1つです。日本では出生率の低下や高齢化が進んでおり、労働人口の減少が深刻な問題となっています。そのため、企業は限られた人材を効率的に活用する必要があり、業務の一部をAIに任せることで、足りない労働力を補えると期待されています。
データ活用の重要性の高まりもAI経営の背景にあります。ビジネスの意思決定には大量のデータが必要不可欠ですが、AIはその膨大なデータを短時間で処理し、企業の戦略立案や意思決定をサポートします。データの分析をAIが担うことで、経営者はより正確な予測を立てることができ、競争力を維持するための重要な武器となります。
このように、AI経営はより効率よく会社を経営し競争力を高める手段として注目されているのです。
AIが活用されている業務

AI経営が注目されている中、実際にどのような業務に導入されているのでしょうか。AIが活用されている場面は主に以下の7つがあります。
- 問合せ対応
- 文章・資料作成
- クリエイティブ作成
- マーケティング
- 採用活動
- 安全管理
- 在庫管理
それぞれ詳しく見ていきましょう。
問合せ対応
まず、挙げられるのが問合せ対応です。
典型的なのは、AIを搭載したチャットボットがサイト上で企業の問合せに対応するケースです。AIが問合せ内容の確認や資料請求の案内などのメッセージを送ります。
また、コールセンターでAIが活用されるケースも少なくありません。AIの音声認識機能を活用し、顧客からの問合せに適切な返答をするシステムが登場しています。
文章・資料作成
文章や資料の作成もAIが得意な分野です。
AIは自然な文章を生成できるため、簡易的な書類の作成に利用されています。Exelと連携してデータを表にするなどの資料作成に活用されることもあります。また、文章の誤字脱字をチェックする校閲を行うことが可能です。
AIは文字起こし機能を活かして、社内会議の議事録を作成し、内容を要約するといった使い方も一般的です。
クリエイティブ作成
企業によってはクリエイティブの作成もAIに任せることがあります。
生成AIを使えば指定した内容に沿って画像を生成でき、広告などのバナーや記事のアイキャッチ画像の作成に便利です。きちんと指示をすれば、通常の写真やイラストと見劣りしない画像を出力できるため、利用する企業が増えています。
また、AIはコードの出力も可能です。Webサイトのコードの草案をAIに書かせるなど、Webデザインの現場で活用されることも少なくありません。
マーケティング
マーケティングもAIが得意な分野の1つです。
AIは過去のデータを学習し、予測を立てることができます。そのため、市場のトレンド予測や需要予測をするのが得意です。例えば、過去の商品の販売データや顧客の属性を学習させれば、売れやすい時期やターゲットにすべき顧客の年齢など、有益な情報を提示してくれます。
従来であれば経営層や従業員が丁寧にデータを分析をする必要がありましたが、AIが代わりにデータ分析を行ってくれるのです。正確なデータを素早く提供してくれるため、経営判断を行うのに役立つでしょう。
採用活動
採用活動もAIが補助できる業務の1つです。
1つ前の見出しで触れた通り、AIはデータの分析ができます。そのため、過去の書類や面接内容を学習させれば、応募者の評価をすることが可能です。採用担当者の代わりにエントリーシートの分析や面接内容の評価を実施でき、自社に合う人材が判定してくれます。
例えば、キリンホールディングスではESの分析や一次面接でAIを用い、応募者の実力を正確に評価する取り組みを実施しました。
出典:PR TIMESAI面接官、キリンホールディングスにトライアル導入決定 | 株式会社レビックグローバルのプレスリリース
安全管理
安全管理の分野でもAIは用いられています。
AIはインターネット上だけでなく、設備やシステムに組み込むことができます。代表的な例が監視カメラです。AIが従業員の動作を監視し、危険を予知した場合にすぐ警告が鳴るようにする、介護の現場で人の転倒を予知して従業員に知らせる、といったシステムがあります。
また、設備の点検もAIは得意です。部品の摩耗やゆがみを監視し、故障を未然に防ぐ取り組みが進められています。
事故を未然に防いだり、設備のメンテナンスをしたりする場面でも、AIは活用されています。
在庫管理
工場や倉庫の在庫管理にもAIは活用されています。
AIを搭載したカメラやシステムが在庫状況を解析し、在庫数の把握や不足品を把握します。システムによっては、発注などの業務も可能です。
過剰在庫や部品不足を防ぎ、適切な量の商品をストックするのに役立つでしょう。
また、コンビニなど一部の店舗では、在庫管理から発展し自動会計にもAIを活用しています。AIが映像をもとに来店者の購入品を把握し、ゲートを通過する際に自動決済するシステムが導入されています。
AI経営をするメリット

さまざまな分野で活用されているAIですが、実際にAI経営を行うことで、会社にどんな恩恵があるのでしょうか。
ここでは、AI経営を行うメリットを解説します。
- 業務効率化につながる
- 人材不足を解消できる
- 経営コストを削減できる
- 意思決定を正確に行える
- 設備を適切に運用できる
- 安全性を向上できる
それぞれ見ていきましょう。
業務効率化につながる
まず注目したいのが業務効率化です。記事を通して触れたとおり、AIは従業員の業務遂行を補助してくれます。業務の草案を代わりに作成してくれる、対応を自動化できるなど、業務の一部を代わりに行ってくれます。簡単な業務であれば、AIで完全に代替できるケースも少なくありません。
AIを導入すれば、業務を短時間でスムーズに進められるようになるでしょう。煩雑な業務を減らし、顧客とのコミュニケーションやアイディアの創出などより価値の高い業務に集中しやすくなります。
人材不足を解消できる
人材不足の解消もAI経営の大きなメリットだと言えます。
従来であれば、業務を適切に進めるためには従業員の人数を確保する必要がありました。しかし、現在はAIが業務遂行を補助してくれるため、新たに雇用する人数を減らせます。今いる従業員のリソースで業務を円滑に進められるでしょう。
また、自社にマッチする人材を雇用しやすくなる効果もあります。採用活動にAIを導入すれば、より多角的かつ正確に応募者を評価できるようになるため、スキルのある社風に合った人材を見つけやすくなるはずです。
経営コストを削減できる
コストカットにつながるのも注目したいポイントです。
直前の見出しで触れたとおり、AIをうまく活用すればより少ない人数で業務を行えるようになり、自社に合った人材の確保にもつながります。場合によっては在籍する従業員の人数を減らせるかもしれません。加えて、業務量が減れば従業員の労働時間も少なくなるはずです。
AIを活用することで人件費を抑えやすくなるでしょう。
意思決定を正確に行える
経営層が正しく意思決定しやすくなることもメリットです。
AIは過去のデータを分析して、トレンドや需要の予測を正確に行ってくれます。例えば、AIに月ごとの自社商品の販売数や顧客の属性を分析させれば、どんな人がいつ商品を買っているのか算出してくれます。結果をもとに、正しい商品の販売時期やターゲットを決められるはずです。
勘に頼った経営を脱却し、よりデータドリブンな会社運営を実現できるでしょう。
設備を適切に運用できる
職場の安全性を高められる点もメリットです。
AIは画像認識が得意なため、設備の監視に活用されます。部品の損耗や故障をいち早く検知し、効率よくメンテナンスを行えるでしょう。突然のトラブルによって商品生産が止まる、納期が遅れるといったトラブルを回避しやすくなります。
安全性を向上できる
最後に、AI経営によって職場環境をより安全にできるでしょう。
前述のとおり、AIを活用すれば設備をきっちり点検できます。故障などのトラブルによって従業員が負傷するのを防ぎやすくなるはずです。
また、AIが搭載されたカメラを設置すれば、従業員が危険な行動をしていないかチェックできます。安全帯の締め忘れや転倒など、怪我につながる行動を未然に防止できるでしょう。
AI経営の成功事例7選

AI経営のメリットに続いて、実際に企業がAIを導入して成功した事例を紹介します。
- 株式会社インターロジック|AI研修を実施して従業員のリテラシーを向上
- ソフトバンク株式会社|エントリーシートの選考時間を75%削減
- 花王株式会社|AIで設備の点検負担を削減
- 住友化学株式会社|生成AIで最大50%の業務効率化を実現
- 株式会社マンダム|生成AIを活用しパッケージのデザインを作成
- セブン&アイホールディングス|AIで発注作業にかかる時間を3割削減
- 千葉市動物公園|来場者データを分析し集客へ活用
各業界から幅広い事例を解説するので参考にしてみてください。
株式会社インターロジック|AI研修を実施して従業員のリテラシーを向上
マーケティング支援を行う株式会社インターロジックは生成AIの活用を検討していましたが、なかなか導入が進まずにいました。従業員がAIについての知識がなく、どう導入を進めればいいかわからなかったためです。
そこで、SHIFT AIが提供する生成AIリテラシーコースを活用。ChatGPTの概要や機能など、生成AIの基礎知識に関する研修を受けました。後のアンケートで、従業員の約70%が生成AIの業務活用に意欲を持つようになったことがわかりました。
従業員のAIリテラシーを向上させたことで、AIを活用する意義が明確になり、AI経営を進める土壌ができた例です。
ソフトバンク株式会社|エントリーシートの選考時間を75%削減
ソフトバンク株式会社では、採用活動を効率よく進めるべく、IBMのAI「Watson」を導入しています。
採用担当が行っていたエントリーシートの選考の一部を、Watsonが代わりに行う形にしました。その結果、選考にかかる時間が約75%削減されました。さらに、2020年からは動画面接の評価にも自社開発のAIを導入。AIが合格基準を満たすと判定した応募者は次の選考に進み、不合格と判断された場合は担当者が確認して合否を決める体制にしました。選考時間の約70%削減が見込まれています。
AIを活用して採用活動を効率よく進めているいい例だと言えるでしょう。
出典:新卒採用選考における動画面接の評価に AIシステムを導入
花王株式会社|AIで設備の点検負担を削減
生活用品を製造・販売する花王株式会社は、商品製造の設備管理に課題を抱えていました。従来は経験豊富なオペレーターが設備の運転データを目視で監視し、異常の兆候を察知していましたが、監視負荷の増大やオペレーターの勘に頼った監視から脱却できずにいました。
そこで、AIを搭載した設備の異常予兆検知システムを導入。AIが運転データをリアルタイムで解析し、異常の兆候を早期に検出することで、設備の安定稼働を実現しました。また、目視監視からAIによる自動監視に移行することで、オペレーターの負担が大幅に軽減されたのです。
加えて、監視作業を行う過程で、若手オペレーターがベテランの知識やノウハウを学ぶ機会が増え、技術継承が進みました。
出典:先進的AI技術を導入したプラントの異常予兆検知の取り組みが第16回日本化学工業協会「レスポンシブル・ケア大賞」を受賞
住友化学株式会社|生成AIで最大50%の業務効率化を実現
住友化学株式会社は、社内向け生成AIサービス「ChatSCC」を開発し、全従業員を対象に運用を開始しました。
ChatSCCは文書作成、校正、プログラムソースコード生成などの一般的な業務に加え、製造データの分析など幅広い業務をサポートします。
事前検証では、約200の典型的な業務パターンでテストし、最大で50%以上の効率化が確認されました。特に、文書作成、校正、メール作成などのシーンでは30%以上の効率化が実現され、大きな効果がありました。
出典:社内向け生成AIサービス「ChatSCC」の運用を開始~飛躍的生産性向上と独自データの有効活用を目指す~ | 事業・製品 | 住友化学株式会社
株式会社マンダム|生成AIを活用しパッケージのデザインを作成
大手美容商品メーカーのマンダムは商品のパッケージデザインにAIを活用しました。
他社が開発した生成AIを用い、商品のパッケージ画像を作成。その後、デザイナーが手直しを加える形でデザインを完成させました。その結果、通常3か月程度かかるデザイン開発期間を1か月半に短縮することにつながりました。
デザインの草案作成にAIを活用し、業務効率化を進めたいい例だと言えます。
出典:『パッケージデザイン用生成AI』を活用したマンダム「冷肌ミスト リフレッシュミント」が新発売 | 株式会社プラグのプレスリリース
セブン&アイホールディングス|AIで発注作業にかかる時間を3割削減
大手スーパーを運営するセブン&アイホールディングスは、イトーヨーカドーの在庫管理の効率化を目的にAIを導入しました。
AIが商品の価格や曜日などをもとに商品の販売数を予測し、発注提案を行ってくれるシステムです。当初は、AIの発注提案を精査する必要がありましたが、徐々に精度が上がり、担当者が発注作業にかける時間が約3割短縮されました。
また、発注業務にかかる時間が減ったことで、他の業務を前倒しで行うことができるなど、業務全体の効率化にもつながっています。
出典:セブン&アイグループが目指すニューノーマル ~新たな顧客体験価値の創出に向けて~ (2021年2月)
千葉市動物公園|来場者データを分析し集客へ活用
千葉市動物公園は、日本システムウエア株式会社とインテル株式会社と協力し、AIによる来場者の分析を実施しました。
入場ゲートで取得できる画像データをAIに読み込ませ、来園者の年齢や性別などの情報を抽出。得られたデータは新たな集客施策に活用される予定です。
AIを活用することで、顧客の属性をより正確に把握し、適切なマーケティング施策を実施しやすくなった事例だと言えるでしょう。
出典:NSW、効率的な施設運営とフードロス削減の実現に向け、インテルおよび千葉市動物公園と協業
AI経営を進めるための4ステップ

AIは企業の経営を大きくサポートしてくれる存在ですが、闇雲に導入しても効果は出づらいでしょう。適切な手順を踏んで導入することがポイントです。
ここではAI経営を行うための4ステップを解説します。
- AIの導入を周知する
- AI導入推進チームを設置する
- 社内研修を行う
- 効果測定を行う
それぞれ詳しく見ていきます。
AIの導入を周知する
まず重要なのが、従業員にAIの導入を伝えることです。
いきなりAIを導入しようとしても、従業員は意義やメリットがわかりません。かえって現場が混乱し、生産性が落ちる可能性もあるでしょう。
なぜAIを導入しようとしてるのか、どんなメリットがあるのかなど、目的や効果をしっかり説明しましょう。従業員の理解が得られれば、よりAIを活用してもらいやすくなるはずです。
AI導入推進チームを設置する
次に、AIの導入を進めるチームを作りましょう。
リーダーシップが発揮され、より導入に向けて従業員が動きやすくなります。新たに推進部門を作る、もしくは各部署に推進を担うメンバーを配置するのが効果的です。
メンバーには、AIに少なからず知見がある従業員を選ぶといいでしょう。AIの活用方法を従業員によりわかりやすく共有できます。また、リーダーシップやマネジメント力のある社員を抜擢し、スムーズに導入が進む体制を整えることも重要です。
社内研修を行う
チームを配置できたら続いて社内研修を実施しましょう。
ただAIを導入しても使い方がわからなければ、うまく活用できません。推進チームが主導でAIの使い方を従業員に説明しましょう。先に推進チームがAIの使い方を学び、その方法を定期的な説明会や勉強会で伝えるのがいいでしょう。
また、AIを活用して成果を出すことにインセンティブをつけ、給料に反映するなど、より積極的に活用してもらえる環境を整えるのも効果的です。
効果測定を行う
最後にAIの導入でどんな効果が得られたかを検証しましょう。
作業がより早く進むようになったのか、販売数は増えたのかなど、いくつか指標を設定して導入前と比較します。従業員にアンケートを行う、数値を計測して分析するなどして効果を把握しましょう。
また、結果をもとに改善点を洗い出すことも重要です。よりAIをうまく活用でき、AI経営を成功させやすくなります。
AI経営を行う際の注意点

最後にAI経営を行う際の注意点を解説します。
- 自社の課題を明確にしておく
- 導入コストを把握する
- 情報の扱いに注意する
ポイントを押さえ、AI経営を成功させやすくしましょう。
自社の課題を明確にしておく
まず、AIの導入前に自社の課題を整理しましょう。
AIは種類によって遂行できる業務が異なります。また、似た製品でも機能に差があることも少なくありません。
どんな課題があるかを知っておくことで、自社に合うAIを選びやすくなります。課題に感じることを経営層で共有し、どんなAIがあるのかをリサーチしておくといいでしょう。闇雲に導入を進めても、課題解決に結びつかなければ効果は得られにくいため注意が必要です。
導入コストを把握する
AIを社内で使うための費用も事前に明確にしておきましょう。
AIは無料のものも多くありますが、有料のサービスも少なくありません。特により複雑な処理が行える、遂行できるタスク量に制限がないなど、高機能なものは料金がかかる可能性があります。また、導入には従業員の研修が必要になるなど、労働時間が伸び、人件費が一時的に増えるかもしれません。
費用対効果が得られそうか把握しておくことで、予算オーバーを防ぎやすくなります。
情報の扱いに注意する
AIを使う上では、情報の取り扱いも慎重にしなければなりません。
顧客の情報や社外秘のデータをAIに読み込ませることで、外部に情報が漏れる危険は否定できません。特に、ChatGPTなどクラウド上で動くものは、情報が運営企業のサーバーに保存され、学習に利用される可能性があります。
情報が外部に保存されないように設定を行うなど、対策が必要です。また、顧客の情報を扱う際には、契約書にその旨を記載するなど、同意を得ておくことが推奨されます。無断で情報を使用するのは避けましょう。
まとめ:AI経営で会社をより効率よく運営しよう
今回はAI経営の概念やメリット、導入手順などについて幅広く解説しました。
AIをうまく活用することができれば、業務効率化や人材不足の解消、コストカットなどさまざまな恩恵があります。会社をより効率よく運営し、従業員が働きやすい環境を整えるのに役立つはずです。
簡単な業務のみAIに任せるなど、取り入れやすいところから使い始めてみましょう。SHIFT AIではAI導入に関する相談を無料で受け付けています。AI経営やAIの使い方など、導入に関することを幅広く相談可能です。また、AIを適切に活用できるAI人材の育成支援も実施しています。AI経営に興味がある、AIの活用を検討している、という方はお気軽にご相談ください。
\ 組織に定着する生成AI導入の進め方を資料で見る /