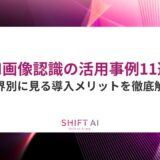「生成AIを導入したものの、いまいち社内で活用しきれていない」「他社はどんなふうに業務で使っているのか知りたい」――そんな悩みを抱える方も多いのではないでしょうか。
実は、生成AIの業務活用は「部署ごとに適した使い方」があります。たとえば、営業部門では提案書の自動作成、人事部門では社内研修のカスタマイズなど、部署ごとに課題も目的も異なるからです。
本記事では、企業が実際に取り組んで成果を出している“部署別の生成AI活用事例”を厳選してご紹介。さらに、成功に向けて押さえておくべき組織的な工夫や、各部署でありがちなつまずきポイントも解説します。
自社に合う活用方法を見つけたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
また下記のリンクからは、「全社員の生成AI活用」「生成AI活用人材育成」をテーマにした複数の事例を含め、AI導入・活用に成功し成果をあげている様々な業種の実際の取り組み17選をまとめた事例集をダウンロードいただけます。自社と似た課題感を持つ会社が、どのようにAIを活用しているのか知りたい方はお気軽にご覧ください。
\ 生成AI導入の『成功イメージ』が実際の取り組み例からわかる /
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
各部署が直面する課題とAI活用の可能性
生成AIの活用は「どの部署でも同じように使えるもの」ではありません。なぜなら、部署ごとに業務内容も課題も大きく異なるからです。ここでは、代表的な5つの部署が抱える業務課題と、生成AIがその解決にどう寄与できるかを整理します。
営業部:提案活動や顧客対応の効率化が課題
営業現場では「提案書作成に時間がかかる」「情報収集やヒアリング内容の整理が負担」といった声が多く聞かれます。生成AIは、過去の提案データをもとにしたドラフト作成や、顧客対応チャットボットの構築などに効果を発揮します。
人事部:採用・育成の業務が煩雑化
人事部門では、求人票の作成、面接質問の設計、研修資料の作成といった業務が属人化しやすく、効率化が難しい領域です。AIを活用することで、職種に応じた文章生成やコンテンツの自動提案が可能になり、作業時間の削減が期待できます。
情報システム部門:問い合わせ対応やルール整備の負担
情シスでは「同じような社内問い合わせが繰り返される」「AI活用に関するルール整備を求められる」といった悩みが顕在化。生成AIは、ナレッジベースと連携した自動応答や、AIリテラシー研修資料の下書き生成にも使われています。
マーケティング部門:コンテンツ量産と分析作業に追われる
企画・マーケティング系の部署では「キャンペーンやLPなどの文案を大量に考える」「データ分析に時間がかかる」などの課題が存在します。生成AIは、キャッチコピーや記事原稿の草案作成、顧客の声の要約・傾向分析といった業務に有効です。
総務・バックオフィス:定型文やマニュアル作成が煩雑
総務などの管理部門では、「社内通知」「稟議書」「備品案内」などの定型文書作成に日々追われていることが多いです。生成AIを導入すれば、文書のテンプレート自動作成や、社内手続きのQ&Aボットなどが実現できます。
\ 生成AI導入の『成功イメージ』が実際の取り組み例からわかる /
部署別・生成AI活用事例と使われているツール
各部署の業務課題に対し、実際にどのような生成AIツールが導入され、どのような成果が出ているのでしょうか。ここでは、主要な部署ごとに代表的な活用事例と使用ツールを紹介します。
営業部|提案書の自動生成にChatGPTを活用
あるIT企業では、営業担当者の提案資料作成にChatGPTを活用。過去の提案実績や業界知見を学習させることで、顧客の業種に合った提案ドラフトを10分で作成できるようになり、営業1人あたりの訪問件数が月20%増加しました。
活用ツール例
- ChatGPT(OpenAI)
- NotionAI(提案メモ整理)
- SalesMarker(ターゲット抽出支援)
人事部|面接質問の設計や研修資料作成に生成AI
大手人材サービス企業では、新卒採用における面接質問案の自動生成と、ロールプレイ研修のシナリオ作成を生成AIに任せています。面接官の準備時間が大幅に短縮され、教育の標準化にもつながっています。
活用ツール例
- ChatGPT+Zapier連携(人材データベースからの自動抽出)
- Kaiber(シナリオ動画作成)
- Slideflow(研修資料の自動構成)
情報システム部門|社内FAQボットとAI活用ルール策定
製造業の情シス部門では、社内ヘルプデスクをAIチャットボット化することで、月間100件以上の問い合わせ対応を削減。さらに、生成AIの利用範囲を部署ごとに明確化した「利用ガイドライン」をAIが下書きする事例も。
活用ツール例
- Helpfeel(AIチャットボット)
- NotionAI(社内マニュアル草案作成)
- SmartHR(FAQ自動回答)
マーケティング部門|記事作成や広告文案に生成AI
SaaS企業では、オウンドメディア記事やSNS広告のタイトル・本文案を複数パターン自動生成。CVRの高いパターンをABテストで選びやすくなり、制作工数は従来の1/3に削減されました。
活用ツール例
- Copy.ai(広告コピー作成)
- CanvaAI(バナー案作成)
- GoogleGemini(検索広告のリライト支援)
総務・バックオフィス|社内通知・手続き案内の効率化
金融系企業の総務部では、社内向け通知文や備品管理フローの説明文をAIに定型化・リライトさせることで、ミスと確認依頼の件数を半減。月1回の稟議チェックもAIレビューでスピードアップ。
活用ツール例
- ChatGPT(文章生成)
- MicrosoftCopilot(Word・Excel内で自動化)
- FormX.ai(申請書類の自動仕分け)
\ 生成AI導入の『成功イメージ』が実際の取り組み例からわかる /
AIツール導入を成功させるためのポイント
生成AIツールの導入を効果的に進めるには、ツール選定だけでなく「導入後の定着」に向けた工夫が欠かせません。ここでは、部署単位でAI活用を根付かせるための具体的なポイントを解説します。
1.部署ごとの業務課題を明確にする
AIツールは「課題解決の手段」であり、目的ではありません。
まずは各部署で、「時間がかかっている業務」や「属人化している作業」などのボトルネックを洗い出すことが重要です。たとえば、営業部なら「提案書作成の属人化」、人事なら「研修資料の作成工数」といった課題がAI導入の出発点になります。
2.試験導入(PoC)で業務適用の可能性を見極める
いきなり全社導入を目指すのではなく、小さく始めて効果を確認するPoC(概念実証)が推奨されます。
たとえば、「人事部で3か月間、研修資料作成に生成AIを使ってみる」といったスモールスタートにより、リスクを抑えてノウハウを蓄積できます。
3.AI活用のルール整備と教育をセットで行う
効果的な導入のためには、「どのような目的で」「誰が」「どこまで使うか」というガイドラインの整備が不可欠です。
さらに、従業員向けのAIリテラシー研修を実施し、現場の不安を解消することで、活用が定着しやすくなります。
参考記事:
社内で使えるAI利用ルールの作り方|チェックリストと雛形付きで徹底解説
4.業務フローへの統合と継続的な改善体制
AIを「業務の一部」として自然に組み込むことで、属人性を排除しやすくなります。
また、「うまくいかなかったケース」を記録・共有し、改善サイクルを回すことで、社内全体の活用精度が上がります。
\ AI導入を成功させ、成果を最大化する考え方を学ぶ /
自社に合ったAI活用を見極めるための“診断”とは?
「AIを導入したいが、どのツールを選べばよいかわからない」「どの部署から始めるのが効果的か判断できない」。
こうした声は、導入検討中の企業によく見られます。そこで有効なのが、「自社の状況を客観的に把握するための診断」です。
1.診断でわかること
生成AIの導入は、企業の業種・規模・業務内容・人材リテラシーによって適した方法が大きく異なります。
「自社はどのレベルの活用ができそうか?」「どのようなツールを優先すべきか?」といった観点をチェックリストやフローチャートで整理することで、導入の方向性が明確になります。
たとえば以下のような診断が有効です。
- 業務の属人化度チェック(→ドキュメント自動生成系AIが有効)
- 従業員のAIリテラシーレベル(→研修ツールから導入するか)
- セキュリティ要件(→オンプレミス対応のAIが必要か)
2.「ツールありき」でなく「活用目的ありき」の視点を持つ
多くの企業が陥るのが、「人気のツールをとりあえず導入する」パターンです。
しかし、診断的なアプローチをとることで、「自社が何を解決したいのか」という本質的な視点に立ち返ることができます。結果的に、ツール選定の精度も高まり、活用の定着率も向上します。
内部リンク提案:
生成AIツール選定の盲点とは?目的別の選び方と導入ステップを解説
3.自社に合う活用方法を見つける“診断ツール”の活用
最近では、簡易な質問に答えるだけで「おすすめツールタイプ」や「導入アプローチ」が見える化される診断コンテンツも登場しています。
導入を検討する企業にとっては、初期判断のガイドとして非常に有効です。
AI経営総合研究所でも、こうした「目的別AI活用診断」機能の提供を検討しています。
まずは自社の状況を客観視し、「どこから・どんな風に始めるか」の方針を固めることが、成功の第一歩となります。
下記リンクからは、自社の生成AI活用力を自己診断できるチェックリストをご覧いただけます。「自社の生成AIへの対応状況を可視化したい」「生成AIの活用に向けて、不足している点を認識したい」といった方はお気軽にご覧ください。
\ セキュリティを含めた自社の「生成AI力」を客観的に判断する /
まとめ:診断的アプローチで、自社に最適な生成AI活用を
生成AIの活用は、もはや一部の先進企業だけの取り組みではありません。
しかし、単にツールを導入するだけでは効果を実感しづらく、「自社に合うかどうか」の見極めが極めて重要です。
本記事で紹介した通り、まずは自社の業務課題やリソース、セキュリティ要件を可視化する“診断的アプローチ”が有効です。
そのうえで、目的に応じたツール選定や導入計画を立てることで、現場に定着しやすくなります。
特に「どの部署から始めるべきか」「誰に使ってもらうべきか」など、導入フェーズの意思決定を効率化するうえでも、診断結果に基づいた判断は強力な武器になります。
下記のリンクからは、「全社員の生成AI活用」「生成AI活用人材育成」をテーマにした複数の事例を含め、AI導入・活用に成功し成果をあげている様々な業種の実際の取り組み17選をまとめた事例集をダウンロードいただけます。自社と似た課題感を持つ会社が、どうやってAIを活用しているのか知りたい方はお気軽にご覧ください。
\ 生成AI導入の『成功イメージ』が実際の取り組み例からわかる /
- Q自社に合う生成AIツールはどうやって見極めればよいですか?
- A
自社の業務課題や目的、ITリテラシーの水準を整理したうえで、「生成系か分析系か」「汎用型か業務特化型か」などの観点でツールの特徴を比較するのが有効です。初期段階では無料トライアルやPoCを活用するのもおすすめです。
- Q診断的アプローチとは何ですか?
- A
自社のAI活用における現状や課題、活用目的を“可視化”し、適切な導入方針を導くプロセスのことです。属人的な判断ではなく、部門横断で客観的に活用レベルを整理することができます。
- Q導入時に最も注意すべき点は何ですか?
- A
ツールの性能よりも、「誰が使うか」「どう使うか」といった“運用設計”が成果に直結します。特にセキュリティルールやプロンプト入力のガイドライン整備、教育体制の有無が、現場での活用定着に大きく影響します。
- Q.無料の生成AI診断ツールはありますか?
- A
一部のコンサル企業やベンダーが無料の簡易診断ツールを提供しています。ただし本格的な活用方針を立てるには、自社の業務や体制に合わせたカスタマイズが必要なケースが多く、専門家の支援も選択肢の一つです。
- Q自社に合った生成AIの研修も受けられますか?
- A
い、SHIFTAIでは診断結果に基づいて研修内容をカスタマイズできる法人向けサービスを提供しています。興味がある方は以下のリンクから詳細資料をご覧ください。