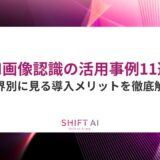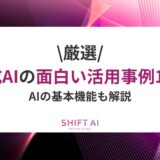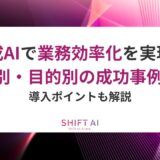「自社に合う生成AIって、どう選べばいいの?」
生成AIの活用が広がる一方で、自社の業務や体制に合わないツールを選んでしまい、思うような成果が出ないケースも少なくありません。
たとえば、
- 「現場に浸透しなかった」
- 「試したけど続かなかった」
- 「リスクが気になって止まっている」
そんな悩みを抱える企業にこそ、“自社に合う活用タイプ”の診断が役立ちます。
本記事では、10問の簡単なチェックリストで、貴社の活用ステージや適したツールタイプがわかる診断コンテンツをご用意。さらに、タイプ別の具体的な活用例やおすすめツール、導入のステップまでをわかりやすく解説します。
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
あなたの会社はどのタイプ?10問でわかる生成AI活用診断
生成AIの導入に失敗しないためには、自社の活用目的や業務環境に合ったアプローチを見極めることが重要です。
以下の10問に「はい」または「いいえ」で答えてみましょう。該当する数によって、貴社におすすめの活用タイプを診断します。
チェックリスト
- 自社ではすでにRPAやSaaSツールの導入実績がある
- 業務マニュアルや社内ドキュメントが多く存在している
- 業務の標準化や属人化の排除に取り組んでいる
- 社内に情報システム部門やDX推進の担当がいる
- セキュリティやコンプライアンスへの配慮が必要な業界である
- ナレッジ共有やFAQ整備の課題がある
- 会議や議事録、報告書作成の効率化に興味がある
- 現場社員がITツールにある程度慣れている
- 試験的にChatGPTなどの生成AIを使ったことがある
- 生成AI導入に向けて経営層も前向きである
診断結果(該当数によって下記に分岐)
- 0〜3個:様子見・情報収集中タイプ
→まずはAIリテラシー向上と業務棚卸から!「AI研修」や「活用マニュアル整備」がおすすめ。 - 4〜6個:部分導入タイプ
→一部部門からスモールスタート。議事録生成・マニュアル作成支援などから始めるのが◎ - 7個以上:全社展開タイプ
→全社的にAI活用に前向き。セキュリティ対応済の法人プラン導入やAIエージェント活用が狙い目です。
診断結果に応じた活用タイプの全体像
前項の診断で、自社がどの活用タイプに当てはまるかおおよその傾向が見えたかと思います。
ここでは、それぞれのタイプに合わせた生成AIの活用ステップや戦略をご紹介します。
タイプ①:様子見・情報収集中(チェック数:0〜3)
特徴
- 生成AIに対する関心はあるが、まだ社内での利用実績は少ない
- AI活用に対する理解度やリテラシーにばらつきがある
- ツール導入よりもまず「何ができるのか知りたい」段階
次にとるべきアクション
- 生成AIの基本やリスクを学ぶ社内研修の実施
- ユースケース事例の収集・共有
- ガイドラインや利用ルールの整備
👉まずは基礎から固めたい方は:AI活用マニュアルの作り方をご覧ください
タイプ②:部分導入・実証実験(チェック数:4〜6)
特徴
- 一部の部署やプロジェクトで試験導入が進んでいる
- 成果が出ているユースケースと、そうでない領域が混在
- 全社導入のための評価・検証フェーズ
次にとるべきアクション
- 成果の出やすい業務(議事録生成、FAQ作成など)にツールを限定導入
- セキュリティやログ管理などの社内基準の検討
- ツールの比較検討とPoCの実施
👉比較検討に迷ったら:法人向け生成AIツール比較ガイドをチェック!
タイプ③:全社展開・業務組込(チェック数:7〜10)
特徴
- 経営層の理解も得られており、AI活用が全社戦略の一部になっている
- 社内教育やツール利用ルールがある程度整備済み
- 「次はどう活用の幅を広げるか」が課題
次にとるべきアクション
- ChatGPTforEnterpriseなどセキュリティ対応済みの法人プランを本格導入
- 業務フローへの統合・API連携
- 全社KPIに紐づくAI活用成果の定量評価
👉実践的な導入なら:ChatGPT法人向けプランの比較記事もぜひご覧ください。
各タイプごとの「最適なAI活用シナリオ」を把握することで、自社に合った次の一手が見えてきます。
自社に合ったツールの選び方|比較すべきポイント
生成AIツールは用途も提供形態も多様です。
導入の目的や、自社のリテラシー・セキュリティ要件に合致していないツールを選ぶと、「使いづらい」「浸透しない」といった結果につながります。ここでは、失敗しないために押さえるべき比較ポイントを解説します。
1.セキュリティ・管理機能
法人利用では「情報漏洩リスク」が最大の懸念です。
次のような観点での確認が不可欠です。
- プロンプトや出力データのログ保存の可否
- ユーザー管理やアクセス制御の仕組み
- データの学習利用の有無(学習OFFが可能か)
- 日本国内でのデータ処理可否(求められる場合)
👉詳しくは:生成AIツールのセキュリティ比較も参照ください。
2.料金体系とコスト感
無料から月額数千円、年契約数百万円まで幅広く存在します。
検討時は、以下のような観点を持つとよいでしょう。
- 利用人数に応じた従量課金or定額制
- API連携やカスタマイズの有無(追加費用の有無)
- 無料トライアル・PoC支援の可否
- 必要十分な機能が過不足なく搭載されているか
※コストだけで判断せず、「運用に乗せられるか」「現場が使えるか」が肝要です。
3.UIの使いやすさ・対応言語
現場で活用が進むかどうかは「使いやすさ」がカギです。
ツールによっては、UIが英語のみ・設定が複雑など、導入の壁になることもあります。
- 日本語UI・マニュアルの有無
- チャット形式or入力フォーム型か
- 初心者でも直感的に操作できるか
4.業務への適合度(テンプレや連携機能)
自社の業務とマッチする機能があるかも重要です。
たとえば以下のような観点でチェックしましょう。
- 「議事録生成」「FAQ作成」など特化テンプレの有無
- 自社業務システム(GoogleWorkspace、Slack、Teams等)との連携可否
- 自動化(RPAやノーコードツール)との連携性
5.ベンダーのサポート体制
特に導入初期は、「何から始めればいいか分からない」というケースが多いです。
ベンダーによる以下のような支援があるとスムーズです。
- 初期設定支援や導入ワークショップ
- 利用状況レポートの提供
- 利用ルール整備の支援やテンプレ提供
- 学習コンテンツやQ&Aの整備
タイプ別|おすすめの生成AIツールと活用例
生成AIツールの選定は、「導入の目的」や「自社の成熟度」によって大きく異なります。
ここでは、以下の4タイプに分けて、おすすめのツールと具体的な活用例を紹介します。
【タイプA】生成AIの試験導入・トライアル段階の企業
▶特徴
- 利用者は一部部署に限定
- 明確な活用ユースケースはまだ模索中
- セキュリティやガイドラインはこれから整備
▶おすすめツール
- NotionAI:社内メモや企画書作成で効果を実感しやすい
- MicrosoftCopilot(Microsoft365):既存のOffice環境で試せる
- ChatGPTTeamプラン:小規模チームでの導入に向く(セキュリティも強化)
▶活用例
- 会議議事録のドラフト作成
- マーケティング文章やSNS投稿の草案生成
- 研修資料・提案書のたたき台作り
【タイプB】業務活用のユースケースが明確な中堅企業
▶特徴
- 部署ごとに活用テーマがあり導入も進行中
- 現場での使い勝手や運用定着が重要
- 課題は「属人化」と「利用ガイドライン整備」
▶おすすめツール
- CopilotforMicrosoft365:全社展開にスケーラブル
- SlackGPT+ワークフロー連携:社内コミュニケーション+自動応答
- 生成AI連携可能なRPAツール(ex:BizRobo!):業務プロセスの自動化
▶活用例
- 営業資料のカスタマイズ生成
- 社内問い合わせの自動対応
- フォーム回答の要約・分析
【タイプC】高度なセキュリティ要件がある大企業・行政
▶特徴
- セキュリティ要件が厳しく、クラウド利用に制限あり
- 組織的に導入する必要がある(ISMS・Pマーク等)
- AI活用に関しては全社ルールが必要
▶おすすめツール
- ChatGPTEnterprise:ログ保存なし・SAML対応・SL契約可
- 国産生成AI(NECLLM、ELYZAなど):国内でのデータ処理に対応
- AzureOpenAIService(PrivateEndpoint構成):環境を分離した構成が可能
▶活用例
- 文書レビューの補助(契約書・規程等)
- プレスリリース・IR文のたたき台作成
- クローズド環境での問い合わせ対応AI構築
【タイプD】部門ごとにAIを開発・拡張したい先進企業
▶特徴
- 自社の業務に特化したAI構築を視野に入れている
- 内製開発力あり、API連携やLLMファインチューニングも可能
- 全社展開済orパイロットが一巡した段階
▶おすすめツール
- OpenAIAPI+自社データベース連携
- Claude3+RetrievalPlugin構成
- LangChain+LlamaIndexベースの社内エージェント
▶活用例
- 社内ナレッジベースと連動したAIチャットボット
- 複雑な業務フローのエージェント化(例:受発注・購買管理)
- データ分析支援AIの構築(BI連携)
診断タイプから導く“適切なスタート地点”を見つけよう
自社が「今どの段階にあるか」によって、選ぶべきツールも導入アプローチも変わります。
導入フェーズごとに、小さな成功体験を積み重ねることが、全社展開の近道です。
診断結果を活かした導入ステップ|社内展開の進め方
自社に合った生成AIのタイプを把握できたら、次はそれを現場にどう根づかせるかが重要です。
ここでは、診断タイプ別に「社内展開を進めるための具体的ステップ」を解説します。
【タイプA】まずは試す|スモールスタートで成功体験をつくる
ステップ
- 少人数チームでPoC(試行導入)
- NotionやChatGPTで簡易業務をAI化
- 使ってみたレポートを可視化・社内共有
✅成功のコツ:いきなり全社に展開せず、業務改善に直結する場面からスタート
【タイプB】活用を広げる|ユースケースを横展開
ステップ
- 部署ごとに活用方針とガイドラインを設定
- Copilot等を使って定型業務の一部を自動化
- 「使っている部署の声」を全社展開の後押しに
✅成功のコツ:AI活用が得意な社員を“アンバサダー”に任命すると拡がりやすい
【タイプC】安全に全社導入|ガバナンスと並行して推進
ステップ
- セキュリティ要件に合うツールの絞り込み
- 情報システム部門と協働で運用ルール策定
- 社内研修+FAQ整備でリテラシー底上げ
✅成功のコツ:IT統制+現場目線のバランスが成功の鍵
社外秘対応やセキュリティ基準の整備については、こちらのガイドも参考にしてください
【タイプD】高度活用へ|自社エージェントの構築・運用体制整備
ステップ
- 内製AIエージェントをパイロット導入(例:社内チャットボット)
- RAG構成やファインチューニングによる精度強化
- 継続的に評価・改善できる“AI活用サイクル”の確立
✅成功のコツ:AI導入=完成ではなく、「継続改善」のプロセスを設計すること
自社に合った“段階的ステップ”が成功の近道
生成AI導入は、ツールを選ぶだけでは終わりません。
「誰が・どこで・どう使うか」を設計し、小さな成功体験から全社展開へとつなげることがカギです。
まとめ|「自社に合う生成AI」は診断から始めよう
生成AIの導入において最も重要なのは、「流行しているから導入する」のではなく、自社の課題や業務に合ったツール・活用方法を見極めることです。
本記事では以下の観点から、自社に最適な生成AIを選ぶ方法を整理しました。
- 自社の業務課題や目的を明確にすること
- 業務タイプ別の活用パターンを知ること
- ツール選定における比較ポイントを理解すること
- 精度・コスト・セキュリティなどで「合う/合わない」が分かれること
- 迷ったときは、無料診断や相談を活用すること
今は、多くの企業が試行錯誤の中にあります。
ですが、「合わないAIツールを選ぶこと」は、業務の非効率や社内のAI不信につながるリスクにもなり得ます。
まずは、自社にフィットするAI活用の方向性を明確にし、小さく試して、確実に成果を出すことから始めてみてください。
- Q自社に合う生成AIツールは、どう選べばいいですか?
- A
業種・業務内容・リソース状況により最適なツールは異なります。まずは「業務のどこを効率化したいか」を明確にし、それに対応できるAI機能(文章生成・要約・分析など)を持つツールを選ぶのが基本です。
- Q無料の生成AIツールではビジネス利用は難しいですか?
- A
小規模な用途なら無料ツールでも可能ですが、セキュリティやカスタマイズ性の面で法人利用には限界があります。業務での本格利用には有料プランや法人向け設計のツールを検討しましょう。
- Q自社の課題が曖昧な状態で生成AIを導入しても意味はありますか?
- A
課題が明確でない状態では、生成AI導入の効果は出にくくなります。まずは「何を改善したいのか(例:資料作成時間の短縮など)」を洗い出すことが重要です。診断コンテンツの活用も有効です。
- Q社内メンバーのAIリテラシーが不安ですが、導入しても大丈夫?
- A
生成AIは専門知識不要でも使えるものが多く、リテラシーの低さは大きな障壁ではありません。ただし、社内研修や利用ルールの整備が鍵になります。導入支援サービスの活用もおすすめです。
- QAI導入に失敗した企業の共通点はありますか?
- A
目的が曖昧なまま導入したり、全社展開を急ぎすぎたりするケースで失敗が見られます。小規模なPoC(試験導入)から始めて検証し、段階的に展開することが成功のポイントです。